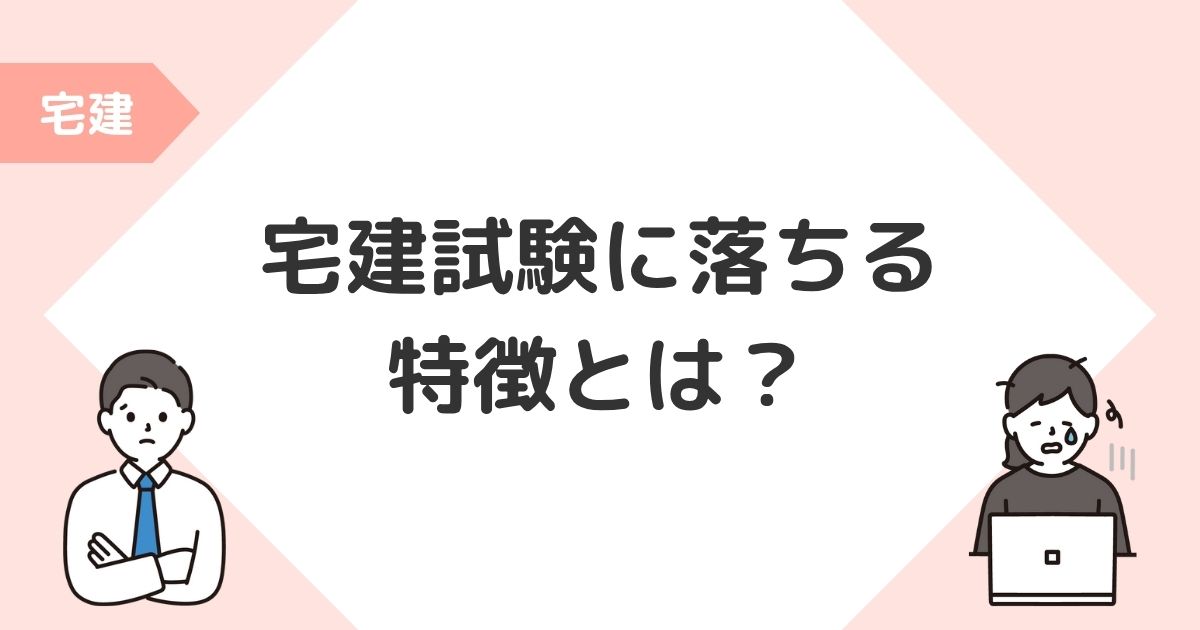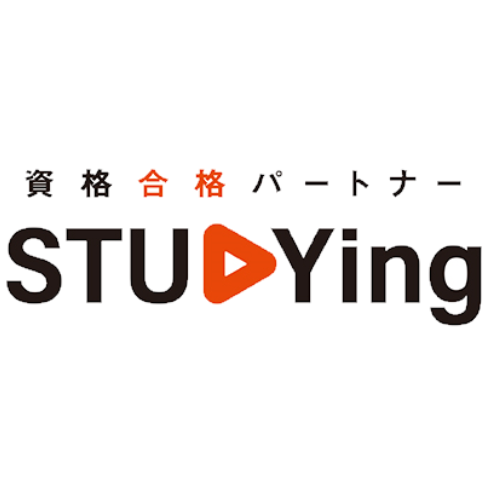宅建試験に落ちる人が多くて不安を感じていませんか?
 ふぁも
ふぁも落ちる人の特徴を踏まえたうえで、しっかりと対策を立てて合格を目指したいですね!
そこで本記事では、宅建試験に落ちる人の特徴や対策、合格するためにやるべきことを紹介します。
最後まで読むことで、宅建試験の失敗パターンを事前に把握でき、対策を立てて効率よく合格できます。
これから本格的に宅建試験の勉強に臨む方は必見です。
「独学の方」や「通信講座にしようか迷っている方」にも朗報!
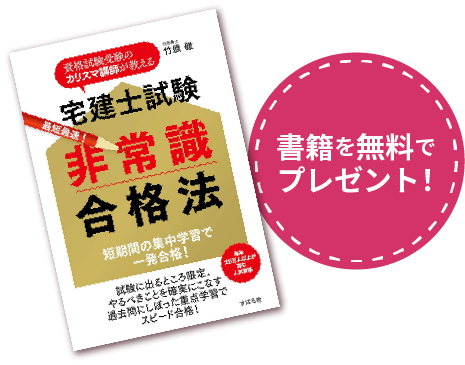
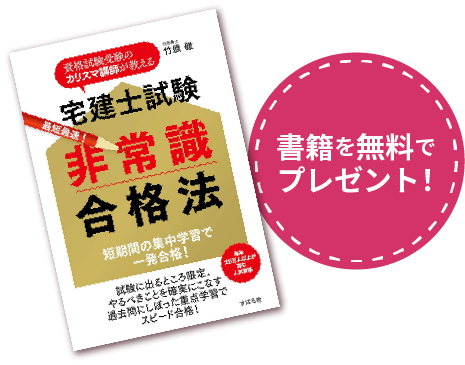
今ならクレアールでは「宅建士試験 非常識合格法」が無料プレゼント中です!
市販で買うと1,650円する書籍が、期間限定で「0円」でもらえます。
- 最短最速で合格が狙える!
- 試験の出題傾向と対策が知れる!
- 合格に必要なポイントだけをおさえた学習法がわかる!
最小努力で合格するコツや本試験直前までの過ごし方など、宅建受験生には必要不可欠な情報が知れます。
いつ終わるか分からないので、合格を目指している方は今すぐにゲットしましょう!
>>「宅建士試験 非常識合格法」をゲットする!
※早い方だと登録は1分で入力完了します!
私も実際に取り寄せましたが、その後のしつこい勧誘・強引な押し売りは一切ありませんでした。
- 宅建やFP2級をはじめ数多くの資格を保有
- Webライターで月20万円超稼ぐ
- 塾講師として1年半・小中高20人以上の生徒を指導


ふぁも
宅建試験に落ちる人の特徴と対策
宅建試験は、受験者の80%以上が落ちる、合格者の方が少ない試験です。
宅建試験に落ちる人の特徴として、大きく3つに分けられます。
それぞれの特徴ごとに対策もあわせて紹介します。
スケジュール・体調管理ができていない
第一に、勉強を始める前の準備が不足していたり、学習中の時間管理が甘かったりすると、宅建試験に落ちる可能性が高まります。
具体的には、以下のことが挙げられます。
| 落ちる人の特徴 | 説明 |
|---|---|
| 勉強時間が足りない・確保していない | 合格に必要な勉強時間を確保できていない |
| スケジュール管理ができていない | 全体像を把握せず、行き当たりばったりで学習を進める |
| 勉強スケジュールを組んでいない | 計画性がなく、その日の気分で勉強を進める |
| 一気に勉強時間を確保しようとする | 無理な計画を立てて挫折しやすい |
| 勉強が長続きしない | モチベーション維持が困難で継続的な学習ができない |
| 作業時間を勉強時間に含める | テキスト整理や教材作成など、直接的な学習ではない時間を「勉強した」と認識してしまう |
| 当日までの体調管理を意識していない | 無理して勉強を進め、試験当日にベストなパフォーマンスを発揮できない |
スケジュール・体調管理ができていない場合は、以下の対策を進めましょう。
| 対策 | 説明 | 具体策 |
|---|---|---|
| 年間・月間・週間計画を作成する | 試験日から逆算して、合格に必要な総勉強時間(一般的に300〜400時間と言われる)を確保する その時間を月、週、日ごとの具体的な学習時間に落とし込む たとえば、「〇月までに宅建業法を完璧にする」「今週は民法の過去問を50問解く」など、具体的な目標と期限を設定する | スケジュール帳やアプリを活用し、進捗を可視化する計画通りに進まなくても、焦らず柔軟に調整する意識が持つ 予備日を確保する |
| スキマ時間を有効活用する | 通勤電車の中、昼休み、家事の合間など、短時間で集中して学習できる スキマ時間を見つけて活用する | スマホやコンパクトなテキストを持ち歩く 一問一答形式の問題を解いたり、重要事項を復習したりする |
| 無理のない範囲で継続できる計画を立てる | 最初から飛ばしすぎず、毎日少しずつ継続できる計画を立てる 無理な計画は挫折の原因になる | 週に一度は必ずオフの日を作る、気分転換の時間を設けるなど、リフレッシュできる時間を組み込む |
| 体調管理を徹底する | 試験本番で最高のパフォーマンスを発揮できるよう、規則正しい生活リズムを心がける 十分な睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動は、記憶力と集中力に繋がる | 試験の1ヶ月前からは、本番と同じ時間帯に学習する習慣をつけ、生活リズムを整える意識を持つ |
スケジュール・体調管理は、宅建試験に合格するのに欠かせない土台です。
漠然と勉強するのではなく、具体的な計画を立てて、実行に移しましょう。
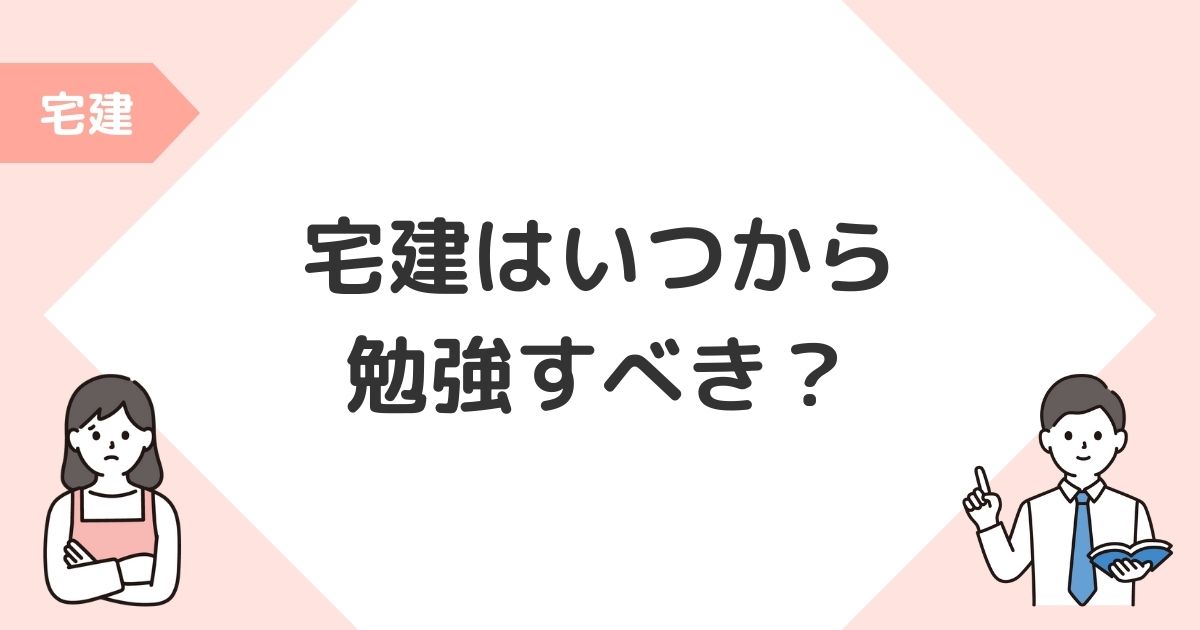
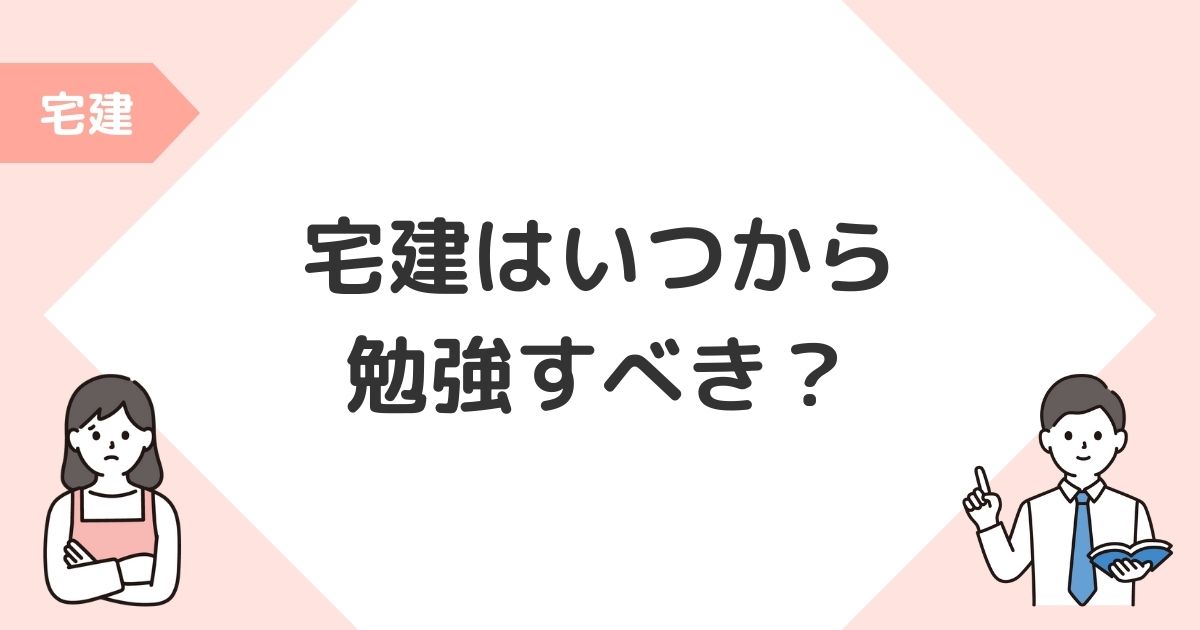
非効率的な勉強法をしている
多くの時間をかけても、以下のように勉強方法が間違っていると、合格には繋がりません。
| 落ちる人の特徴 | 説明 |
|---|---|
| アウトプット(問題演習)が不足している | インプットに偏っており、知識を解答に使える形にできていない |
| 内容を理解せずになんとなくで過去問を解いている | 答えを丸暗記しているだけで、本質を理解していない |
| 誤った過去問の使い方をしてしまう | 解きっぱなしで、過去問を解く目的や効果的な使い方を理解していない |
| 丸暗記や語呂合わせに頼っている | 暗記だけで乗り切ろうとし、応用が利かない |
| テキストを隅々まで細かく読む・完璧を求める | 細かすぎる部分や満点を目指すあまり、非効率な勉強に陥る |
| 出題頻度を考えずに、試験に出ない不必要な知識まで覚える | 重要度の低い部分に時間をかけすぎる |
| 誤った方法で自分に合っていない勉強をする | 勉強法や自分に合った学習スタイルを確立できていない |
| テキストを読んだり授業や講座を視聴したり、インプットだけで満足してしまう | 「わかったつもり」になり、演習や復習を怠る |
| 宅建業法をおろそかにする | 得点源となる重要科目を軽視する |
非効率的な勉強をしないためにも、以下の対策を進めることが大事です。
| 対策 | 説明 | 具体策 |
|---|---|---|
| インプットとアウトプットのバランスを保つ | インプット(例:テキストを読む)だけでなく、アウトプット(問題集を解く)の時間も確保する インプット:アウトプット=2:8を目安に進める | テキストを一通り読んだら、すぐに該当する範囲の過去問を解き、知識が使えるか試す習慣をつける |
| 過去問は「なぜ?」を意識して解く | 過去問は、単に正解を覚えるのではなく、「なぜこの選択肢が正解なのか」「なぜこの選択肢は間違いなのか」を徹底的に考える 根拠となる知識を遡って理解する | 間違えた問題だけでなく、正解した問題についても、すべての選択肢の正誤理由を説明できるまで深掘りする |
| 苦手分野から逃げない | 宅建試験は、1点の正誤で合否を分けるため、権利関係をはじめ、理解に時間がかかる苦手分野から逃げない できる限り捨てる範囲は最小限に抑える | 苦手分野のテキストや解説動画を繰り返し見たり、個別指導や質問サービスを活用したりして、疑問点を解消する |
| 重要度と出題頻度を意識した学習をする | すべての範囲を完璧にしようとせず、宅建業法をはじめ、出題頻度の高い分野や得点源になる分野から優先的に学習する | 過去問を分析し、どの分野がよく出題されるのか、どの内容が重要なのかを把握する |
| 「満点」ではなく「合格点」を目指す | 完璧主義に陥ると、試験に出ないような細かい知識に時間をかけすぎてしまう 宅建試験は満点を取る必要はない 合格点(例年36点前後)を確実に取ることを目標にする | 捨てるべき問題や分野を決め、重点的に学習する範囲を絞り込む勇気も必要となる |
ただ闇雲に勉強するのではなく、効率的かつ効果的な学習方法を取り入れることが、合格への鍵となります。
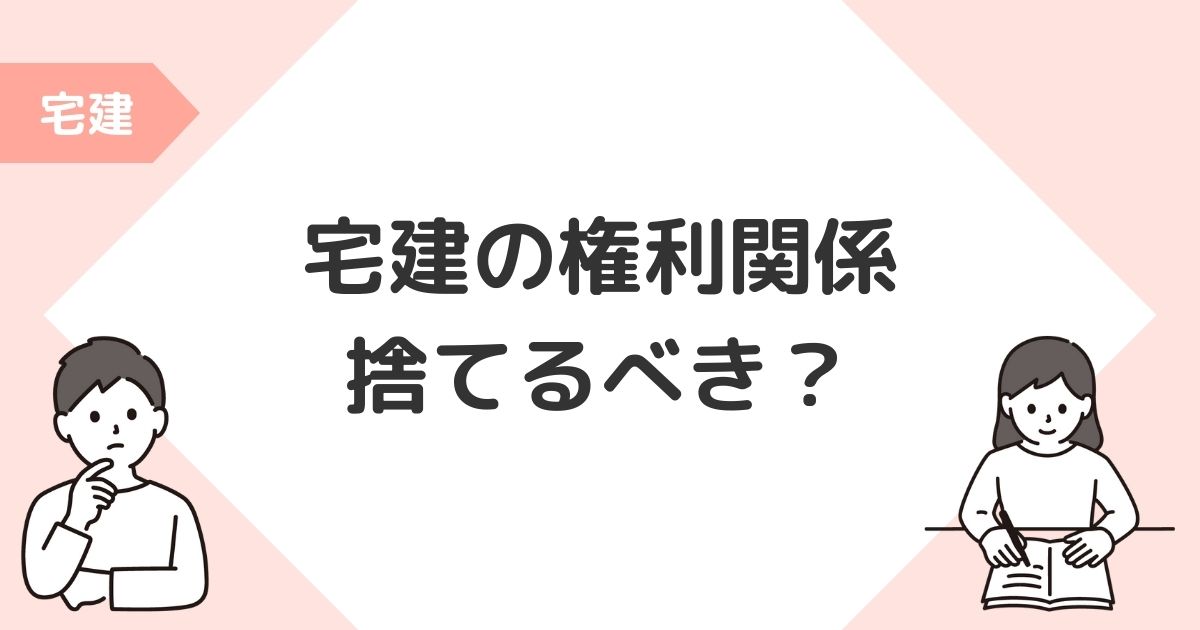
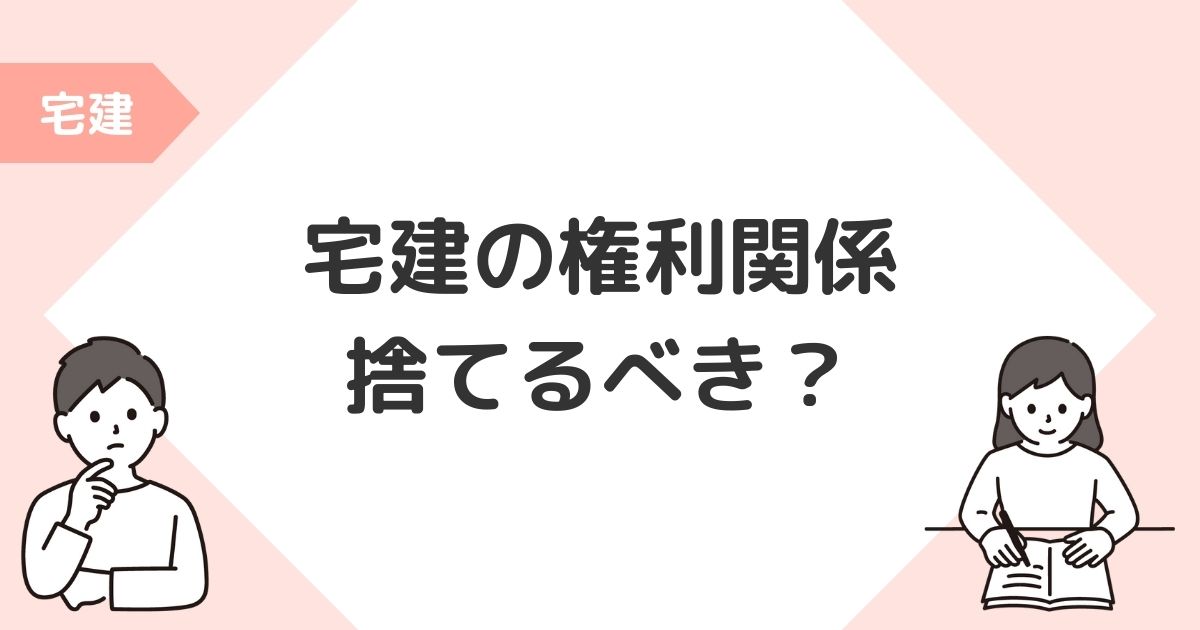
試験対策・戦略が十分ではない
試験本番で実力を発揮するための準備や戦略が不十分だと、試験に焦って落ちる可能性が高まります。
具体的には、以下のことが該当します。
| 落ちる人の特徴 | 説明 |
|---|---|
| 試験本番での時間の使い方が身についていない | 過去問や模試などで時間配分の練習をしていない |
| 宅建試験の内容がわかっていない | 各科目の特性や重要度を理解せず、バランスの悪い学習をしている |
| 使う教材が合格に適していない・いろんな教材に手を出そうとする | 教材選びに失敗したり、教材を絞り込めずに混乱したりする |
| 試験のテクニックを知らない | 効果的な問題の解き方や戦略を学んでいない |
| 予想模試がそのまま出題されると思っている | 模試の目的を誤解し、過度な期待を抱く |
本番で実力を最大限に発揮するためにも、以下の対策を実行するのが望ましいです。
| 対策 | 説明 | 具体策 |
|---|---|---|
| 過去問や模試を活用して時間配分の練習をする | 試験本番と同じ時間(2時間)で50問を一度に解く練習をする 過去問や模試で一通りの問題を解くことで、各科目にどれくらいの時間をかけるべきか、自分なりの最適な時間配分を身に付けられる | 過去問を解く際は、静かな環境でマークシートを用いて進める 模試は、試験会場の雰囲気に慣れる良い機会となる |
| 最新の法改正情報を確認する | 宅建試験は法改正の影響を受ける場合があるため、最新の情報を確認する | 法改正情報をネットで調べたり、最新の法改正に対応したテキストや問題集を利用したりする 試験直前には最終確認を忘れずに行う |
| 自分に合った教材と勉強法を見つける | 近頃、さまざまな教材や勉強法があるが、万人にとっての正解はない 無料の資料請求や体験授業などを活用し、自分に最も合った教材や学習スタイルを見つける | 学習スタイルとして、独学、通信講座、通学講座の3種類ある テキスト、問題集、動画講義などを比較検討し、継続できるものを選ぶ |
これらの対策を地道に実行することで、宅建試験の合格に近づくことが可能です。
諦めずに、計画的に勉強を進めていきましょう。
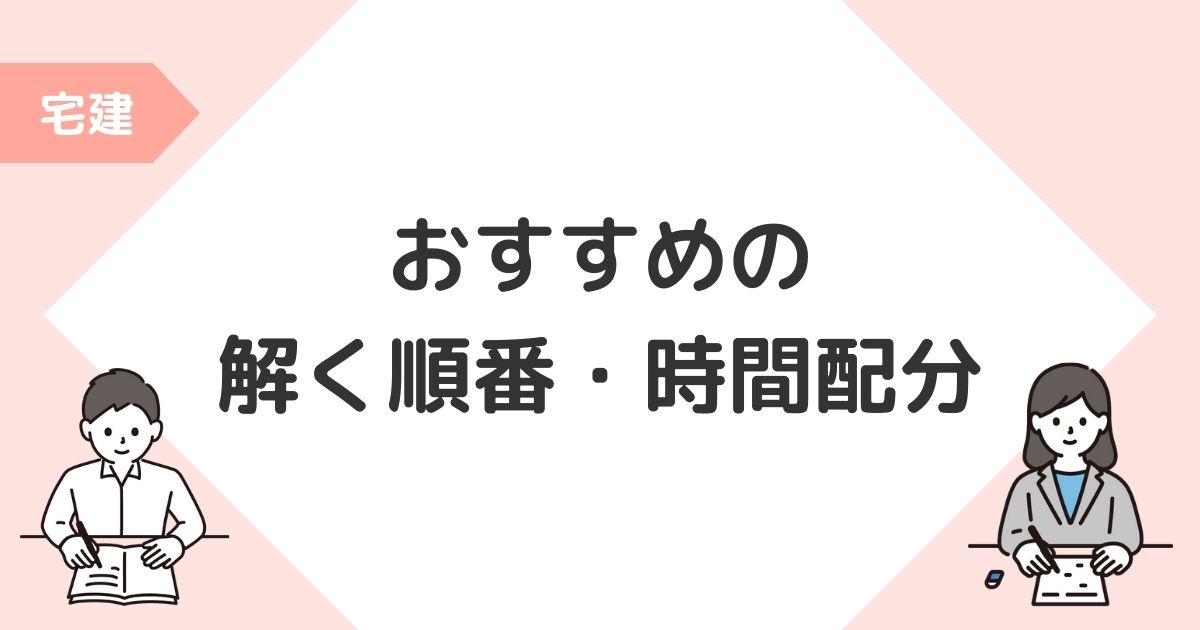
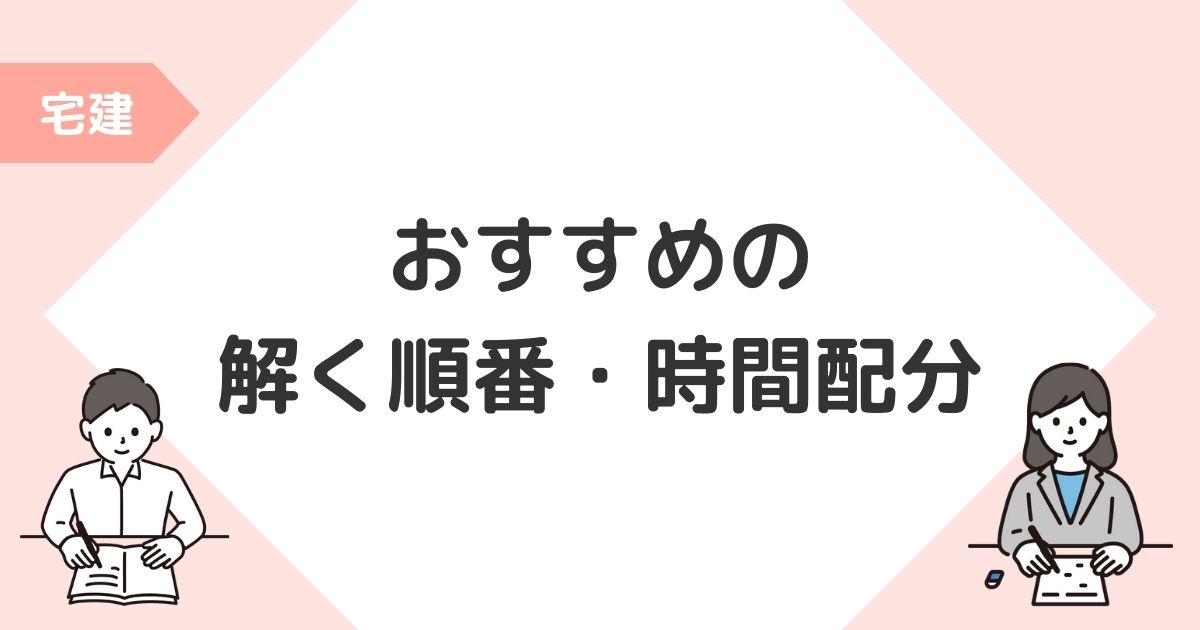
宅建試験に落ちる人の特徴に該当しそうな方がやるべきこと
宅建試験に落ちる人の特徴はわかったけど、まず何から始めれば良いかわからない」という方もいるはずです。
ここでは、宅建試験の合格を目指している方が勉強前にやるべきことを紹介します。
正しい方向で勉強を進めるためにも、下準備は欠かせません。
1つずつステップを踏んで、良いスタートダッシュを切りましょう!
宅建試験の概要・勉強法を把握する
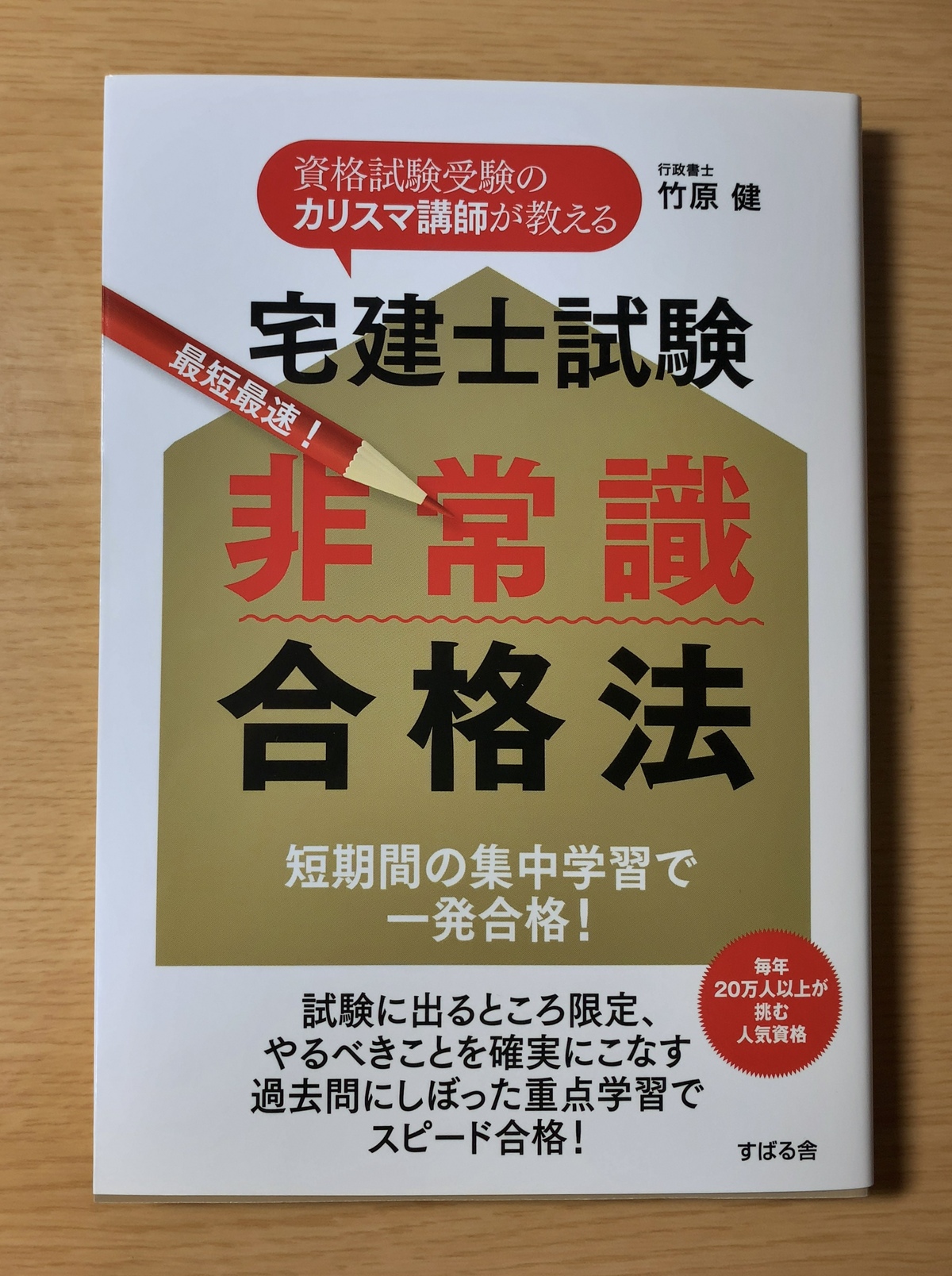
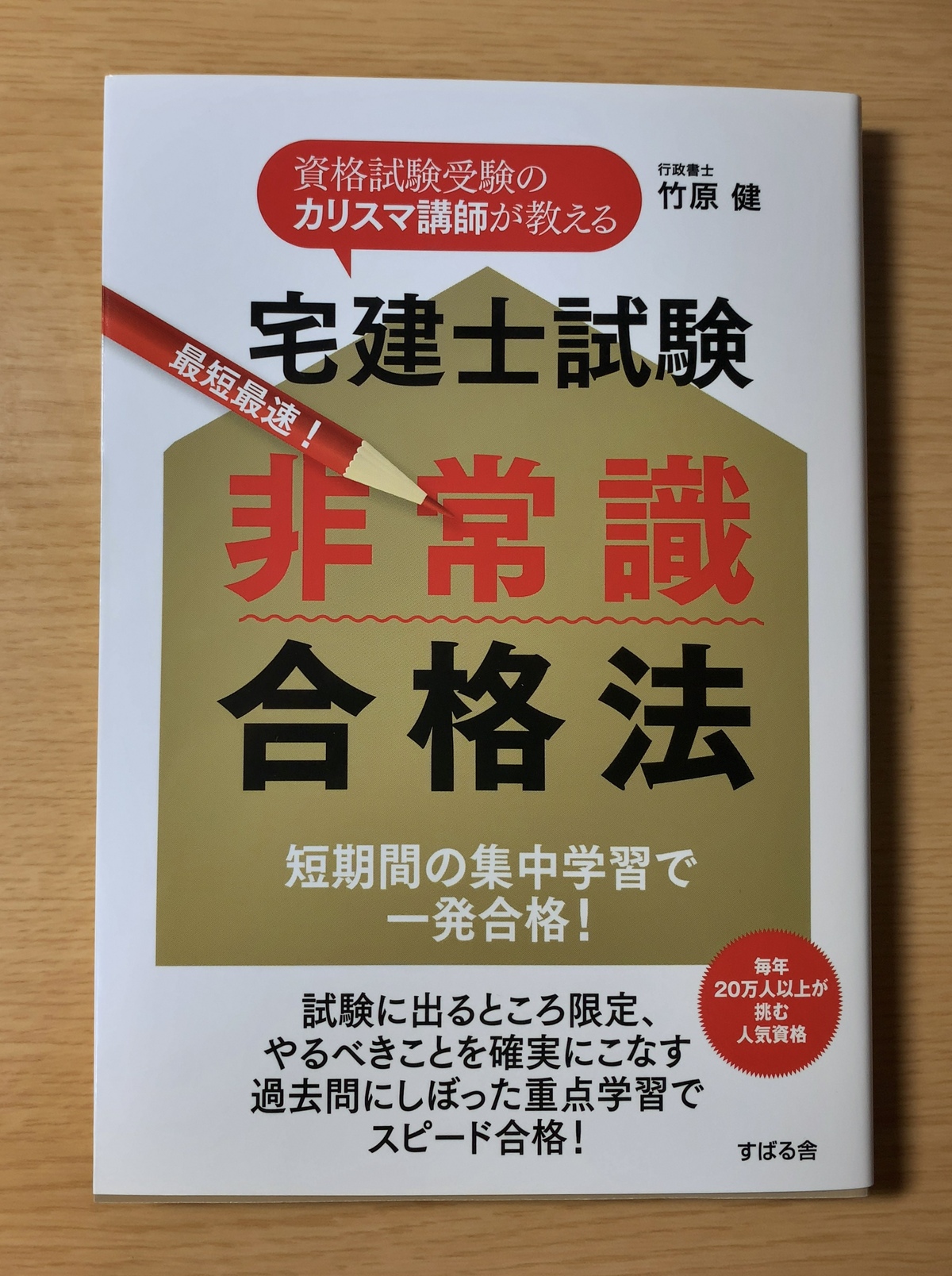
宅建試験の合格を目指すためにも、まずは宅建試験の全体像や効果的な勉強法を理解することが重要です。
インターネットでの情報収集も有効ですが、情報が多岐にわたり、効率が悪いと感じる方もいるはずです。
そこで、クレアールが無料で提供している書籍「非常識合格法」を活用することで、手軽に効率良く必要な情報を得られます。
非常識合格法を読むことで、以下の重要なポイントを把握できます。
- 宅建試験の概要・特徴
- 試験の出題傾向
- 過去問を活用した学習方法
- 試験直前や前日の具体的なアドバイス
- 試験に出る頻出箇所や学習の要点を絞った学習範囲
これにより、無駄な労力をかけずに、合格を目指すことが可能です。
もちろん、非常識合格法は講座を受講する必要はなく、無料登録をするだけで入手できます。
しつこい勧誘はありませんので、この機会にぜひ手に入れてみてください。
\早い者勝ち!カンタン1分で入力完了/
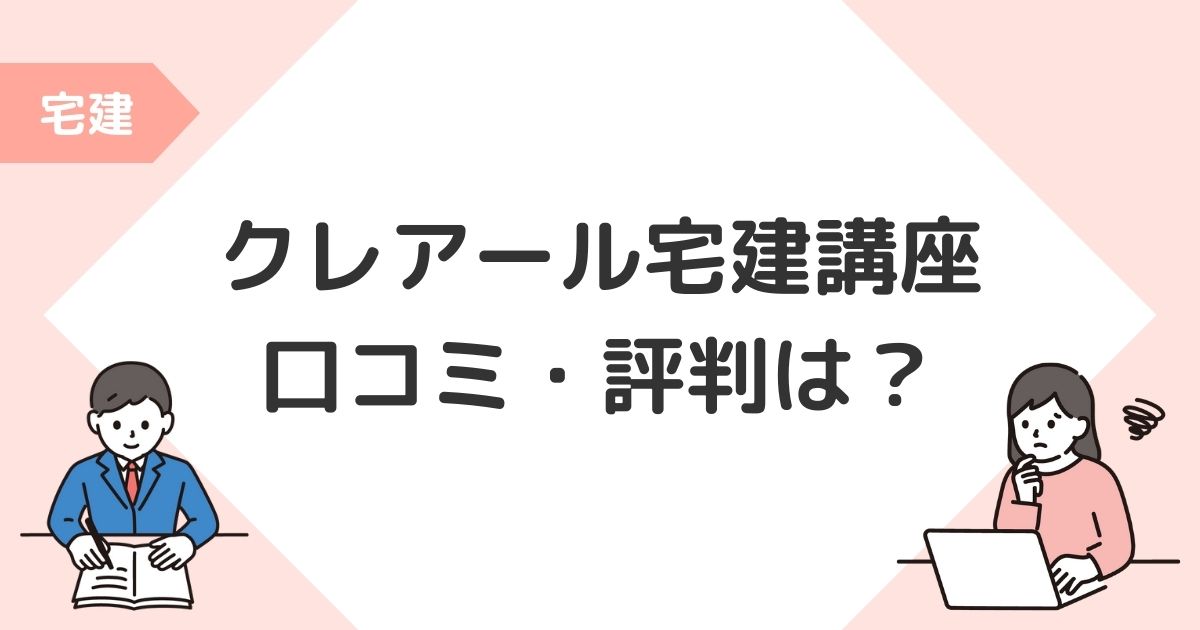
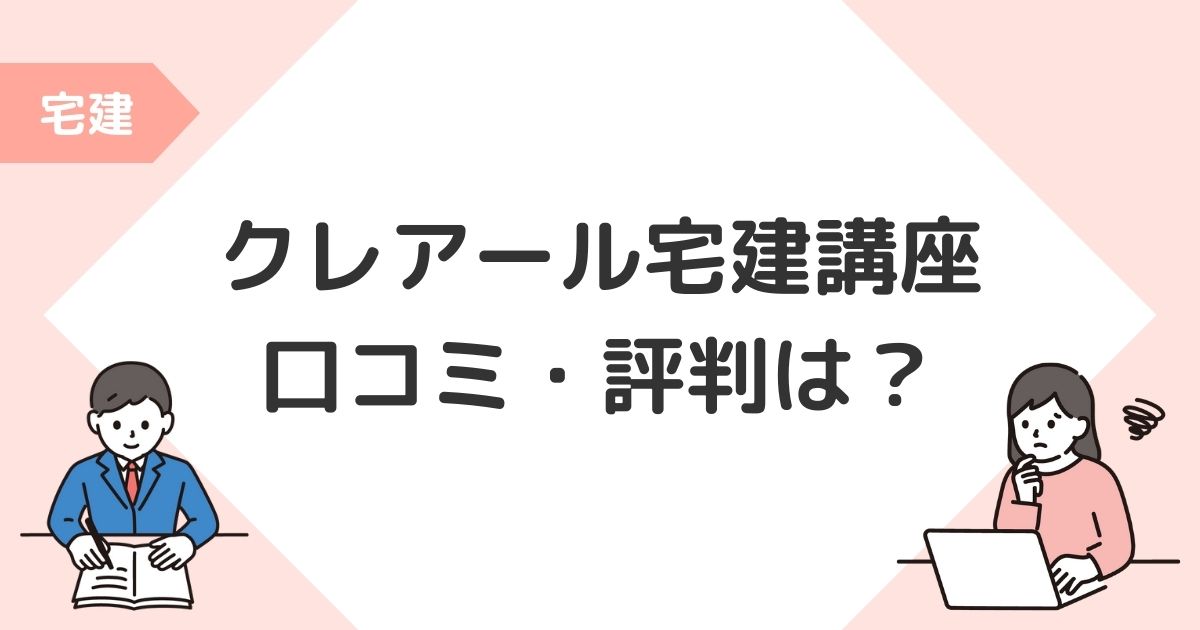
勉強期間を多めに確保する
勉強期間は、余裕を持ってスケジュールを立てることが大切です。
勉強が苦手な方や、長期間学習から離れていた方がいきなり無理な計画を立てると、すぐに挫折してしまう恐れがあります。



たとえ、学力に自信がある方でも、無理な計画は挫折の原因となりますよ。
挫折しないためにも、周囲の勉強期間や学習時間に流されず、自分のペースで着実に勉強を進めることが重要です。
また、仕事や家事で忙しい方は、1日に確保できる学習時間が限られるため、全体を通して勉強期間を長めに設定しましょう。
一般的に、試験日(10月中旬)から逆算して、6か月前にあたる「2月中旬頃」から学習を開始するのがおすすめです。
2月中旬から毎日2時間の勉強を続ければ、試験日までに合計500時間の学習時間を達成できる計算になります。



もちろん、人によって必要な勉強時間や確保できる時間は異なるため、勉強期間は一概には決められません。
自分のライフスタイルやこれまでの学習経験に合わせて、自由に学習計画をカスタマイズしてくださいね!
詳しい計算方法については、以下の記事を参考にしてください。
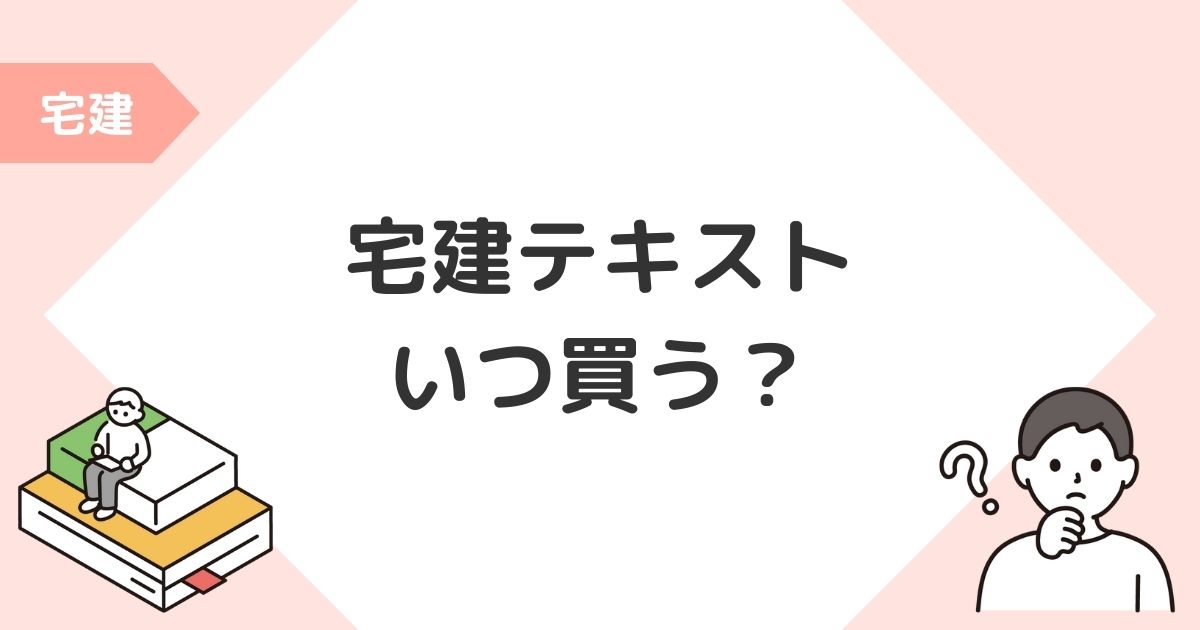
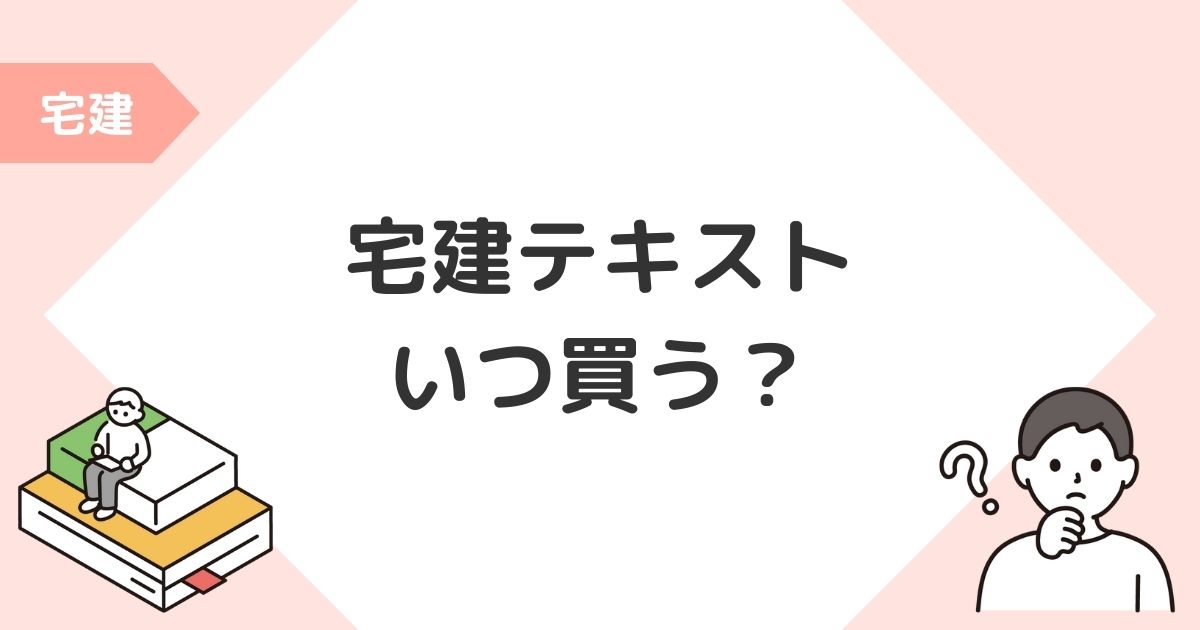
3つの学習スタイルから選択する
宅建試験の学習には、大きく分けて以下の3種類のスタイルがあります。
自分の状況に合わせて最適なものを選びましょう。
| 学習スタイル | 特徴 | 費用目安 |
|---|---|---|
| 独学 | お金がかからない 自分のペースで勉強できる 自らスケジュール管理する必要がある | 1万円以内 |
| 通信講座 | 効率良く学べる 自宅から好きな時間で学習できる すぐに質問できない | 6万円前後 |
| 通学講座 | 講師と対面で学べる 他の受験生と一緒に勉強できる お金がかかる | 10万円前後 |
どの勉強法を選ぶかは人によって異なるため、それぞれの特徴をよく理解したうえで選択しましょう。
基本的には、費用を安く抑えたいなら「独学」、効率を重視するなら「通信講座」が主な選択肢となります。
テキスト選びや通信講座選びに迷っている方は、以下の記事を参考にしてください。
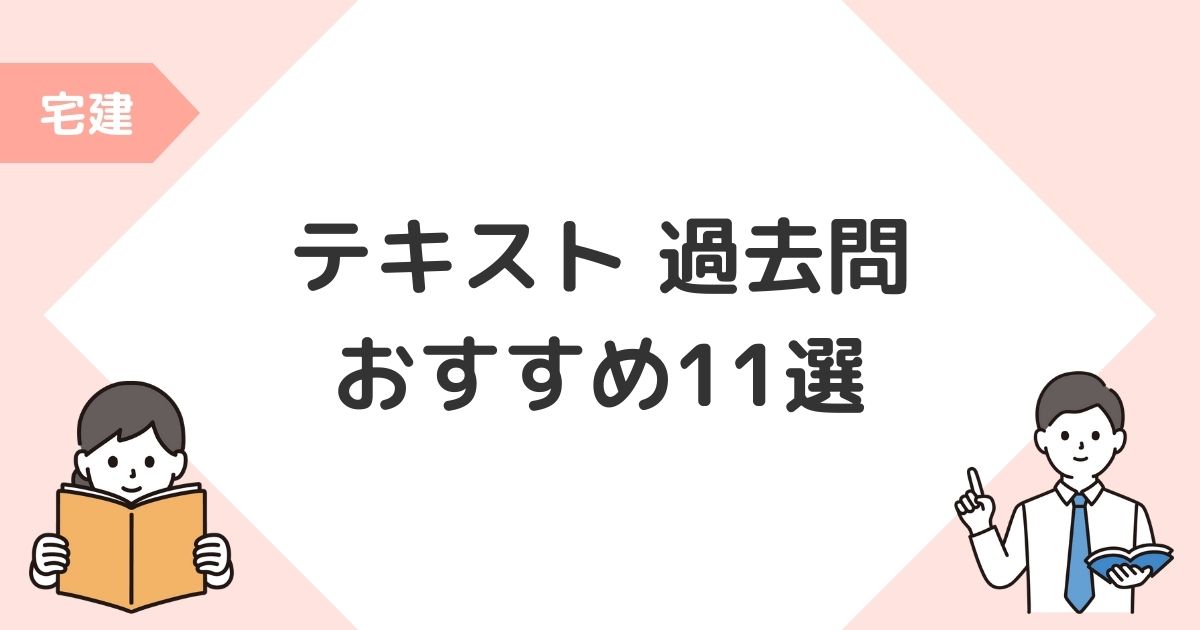
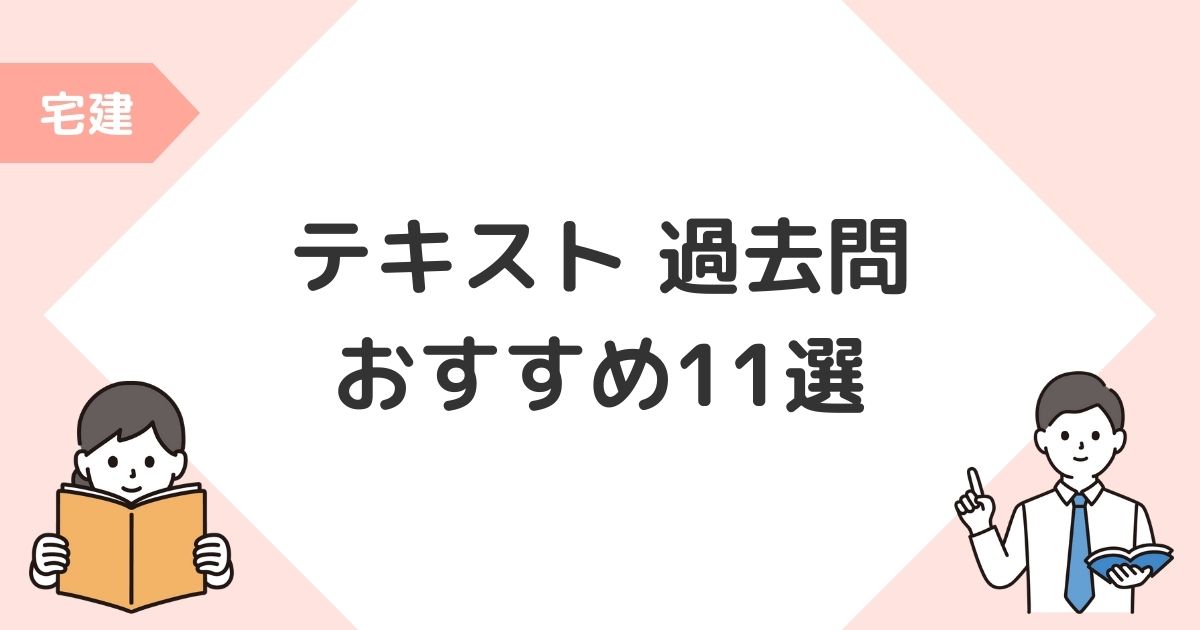
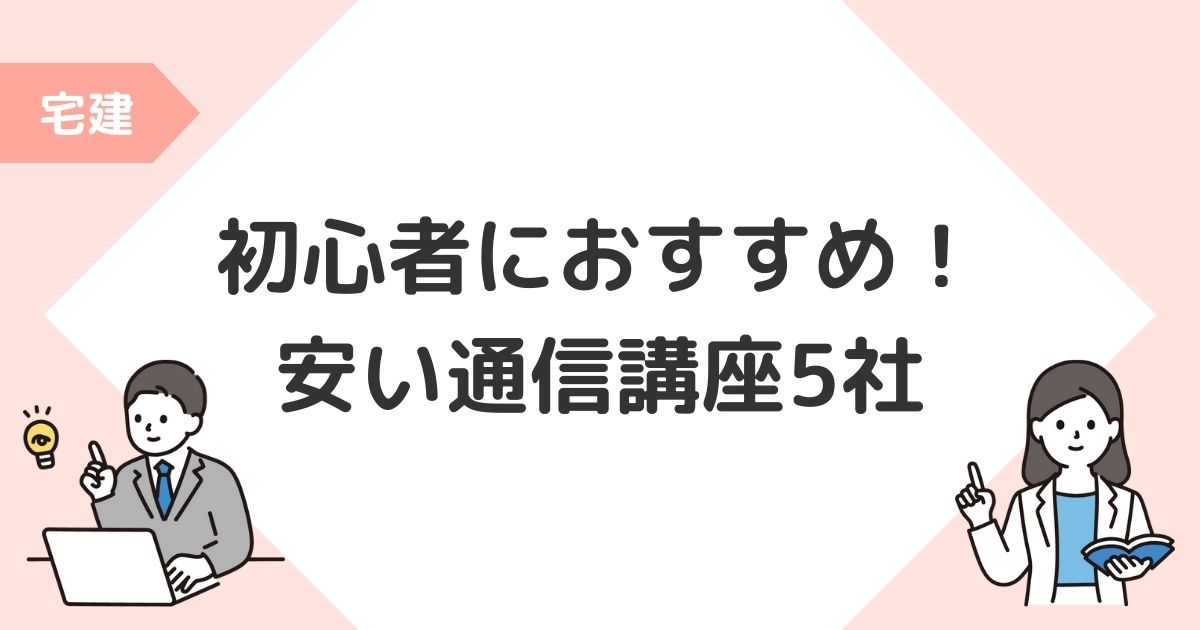
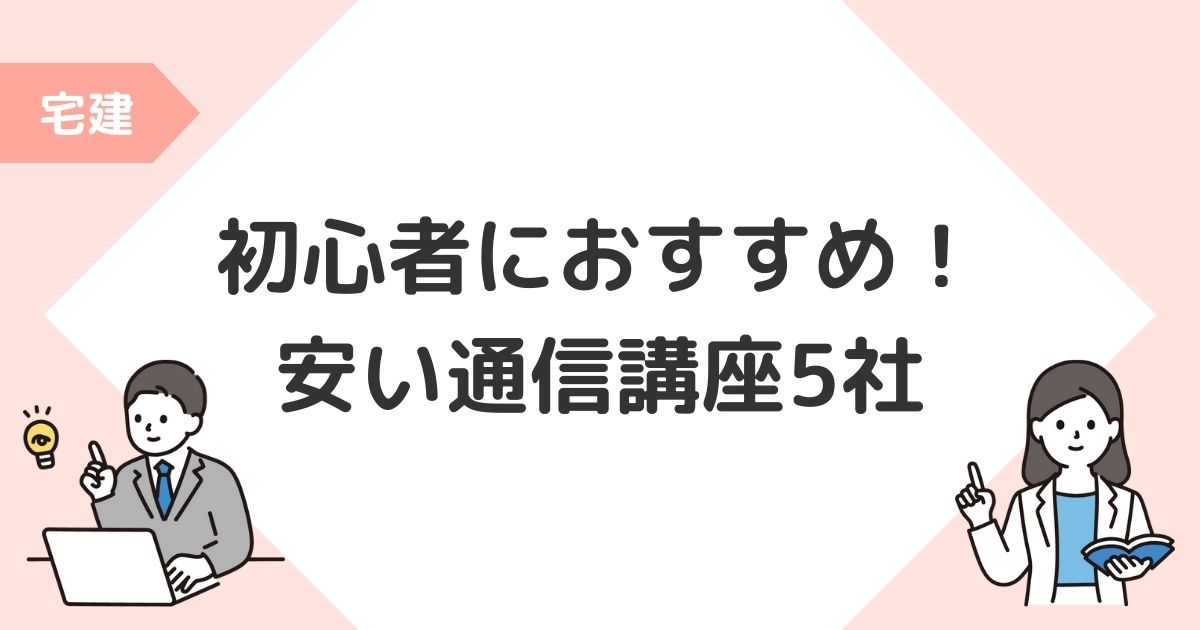
独学でおすすめのシリーズ
独学の場合、トリセツシリーズを買い揃えるのがおすすめです。
無料講義動画が充実しており、初学者の方も読みやすいのが特徴です。
おすすめの通信講座
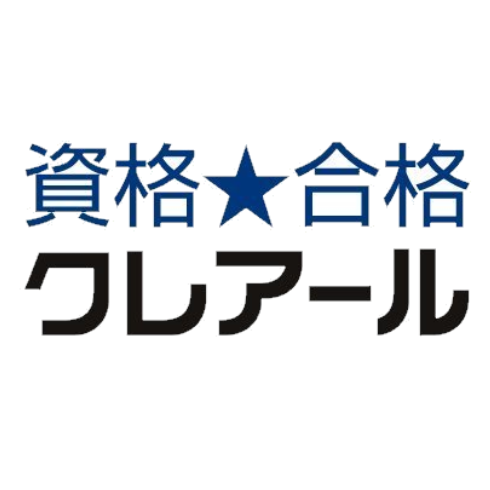
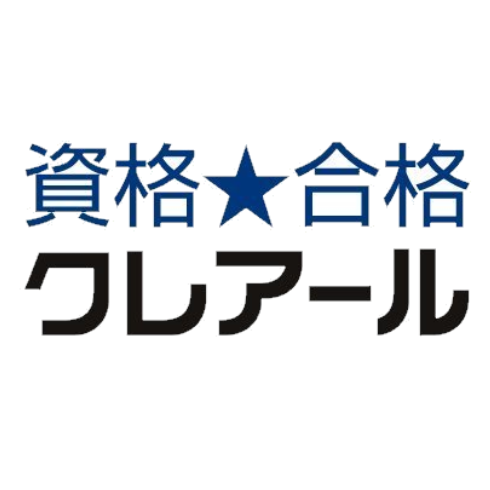
クレアールは、1998年に開講した長年のノウハウがある講座です。
セーフティコースを利用して今年の試験に合格すると、トータルで実質負担が33,434円に抑えられます。
本試験の受験料(8,200円)もクレアールが出してくれるので、お得に最短で合格を目指せます。



コースはいくつかあるので、まずは資料を取り寄せて内容を確認するのがおすすめです。
今ならクレアールの書籍「宅建士試験 非常識合格法」も無料でゲットでき、情報収集に役に立ちます。
\早い者勝ち!カンタン1分で入力完了/
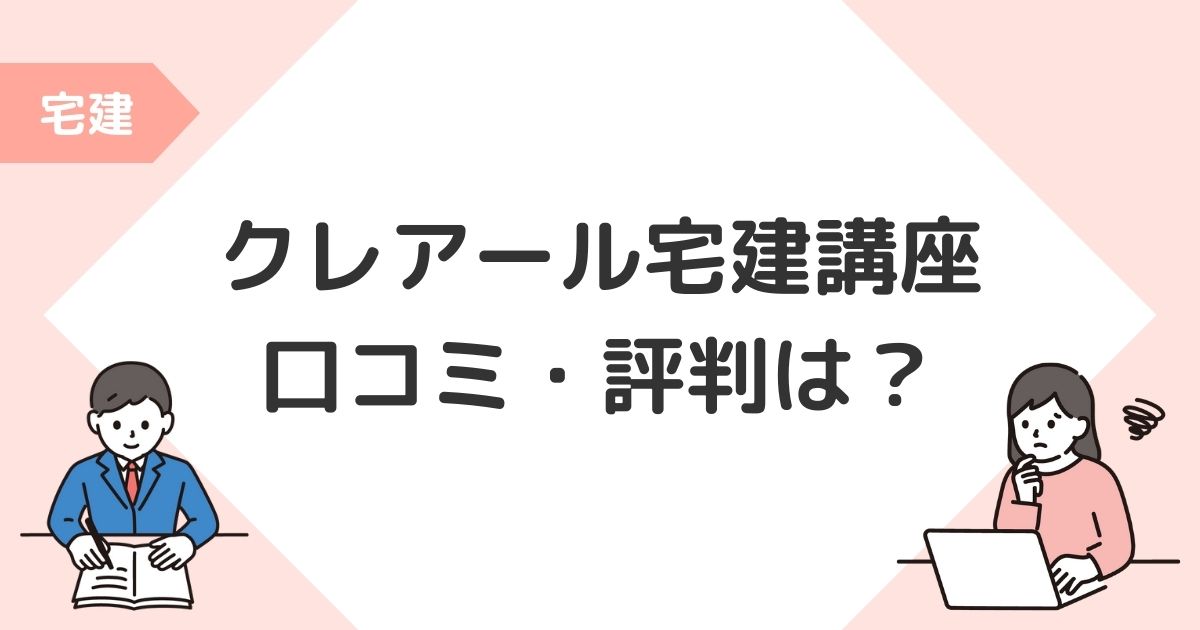
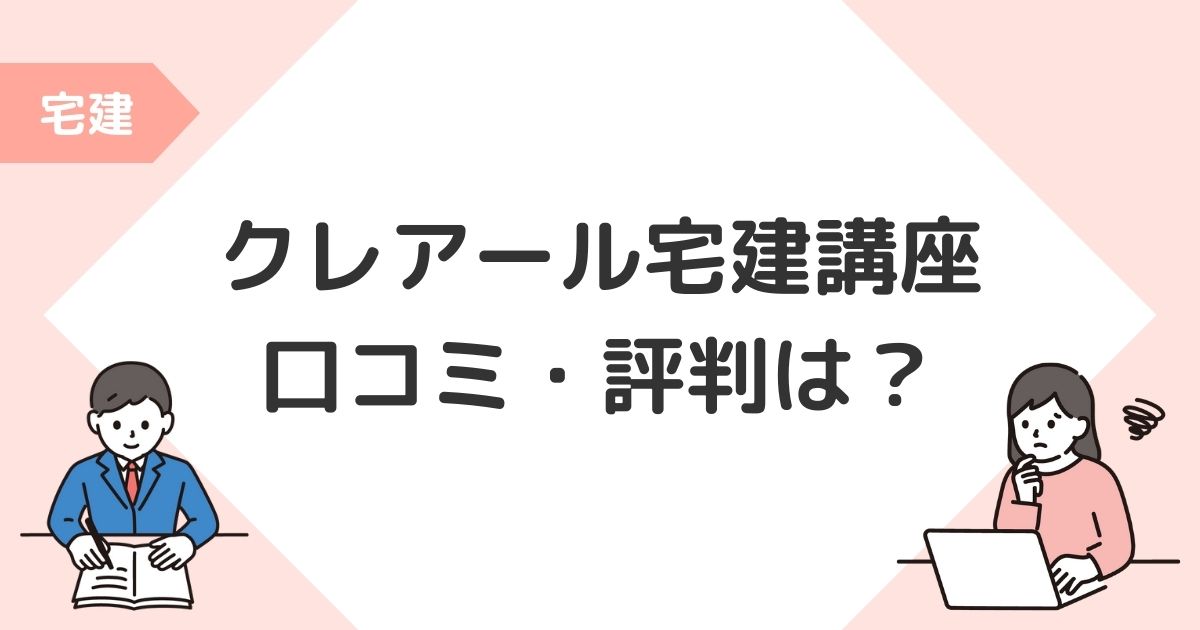
宅建試験に落ちる人の特徴を踏まえて対策を立てよう!
宅建試験に不合格となる人には、共通の特徴が見られます。
その中で最も多いのは、計画性のない学習です。
漫然とテキストを読むだけ、過去問を解きっぱなしにするなど、アウトプット不足や復習の甘さが目立ちます。
これらの落ちる人の特徴を踏まえて試験に合格するためには、最初に具体的な学習計画を立て、着実に実行することが大事です。
特に、過去問はしっかりと行い、間違えた問題は理解できるまで繰り返しましょう。
徹底した自己分析と計画的な学習で、合格を掴み取りましょう。