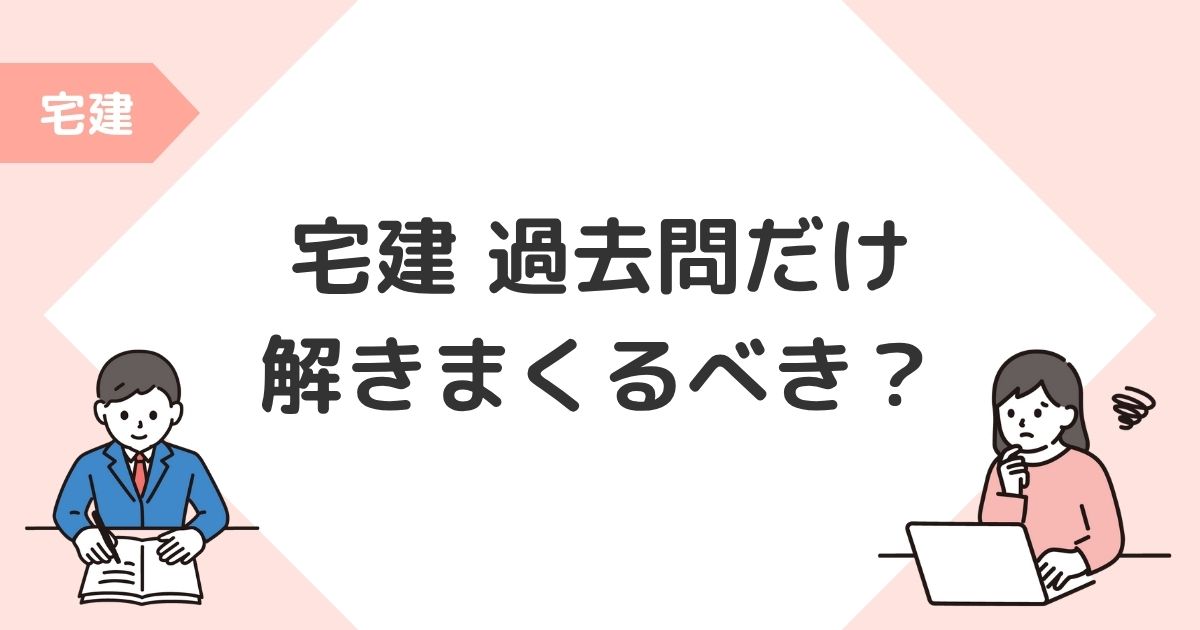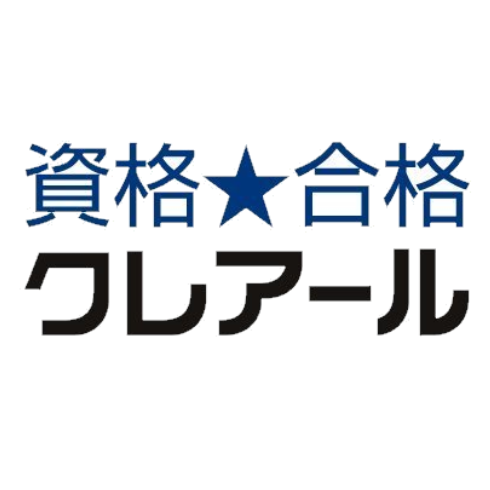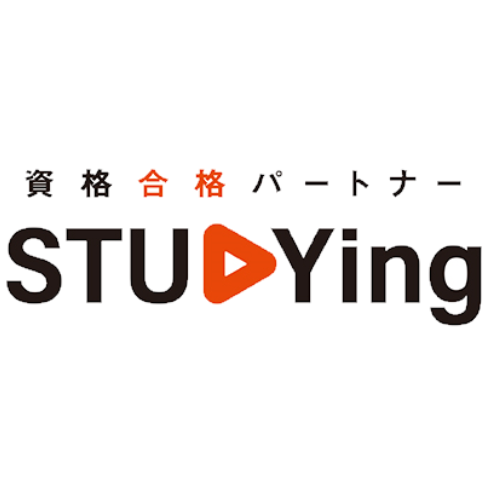宅建は過去問だけで合格できるのか疑問を抱いていませんか?
 ふぁも
ふぁもできればお金をかけずに、受験勉強を済ませたいですよね!
そこで本記事では、宅建の過去問だけを解きまくるべきかに対する回答に、落ちた人の特徴や問題を覚えてしまうときの対処法を紹介します。
最後まで読むことで、宅建の過去問を用いた効率的な学習法がわかるはずです。
宅建試験の合格に繋がる過去問の活用法を知りたい方は必見です。
「独学の方」や「通信講座にしようか迷っている方」にも朗報!
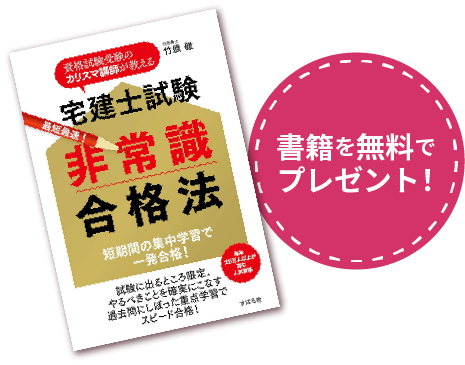
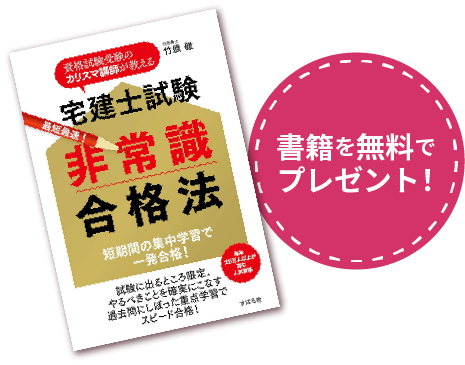
今ならクレアールでは「宅建士試験 非常識合格法」が無料プレゼント中です!
市販で買うと1,650円する書籍が、期間限定で「0円」でもらえます。
- 最短最速で合格が狙える!
- 試験の出題傾向と対策が知れる!
- 合格に必要なポイントだけをおさえた学習法がわかる!
最小努力で合格するコツや本試験直前までの過ごし方など、宅建受験生には必要不可欠な情報が知れます。
いつ終わるか分からないので、合格を目指している方は今すぐにゲットしましょう!
>>「宅建士試験 非常識合格法」をゲットする!
※早い方だと登録は1分で入力完了します!
私も実際に取り寄せましたが、その後のしつこい勧誘・強引な押し売りは一切ありませんでした。
- 宅建やFP2級をはじめ数多くの資格を保有
- Webライターで月20万円超稼ぐ
- 塾講師として1年半・小中高20人以上の生徒を指導


ふぁも
宅建は過去問だけを解きまくるべき?
「過去問だけ」というのは、2つの意味として捉えることが可能です。
- 基本テキストは買わず過去問だけ
- アウトプットの教材は過去問だけ
また、過去問には分野別と年度別の2種類あります。
【結論】テキストも必要!過去問は分野別と年度別の2冊を解きまくるべき
宅建には、過去問に加えてテキストも必要となります。
なぜなら、知識を深めたり内容を復習したりする際にテキストがあると効率的だからです。
また、過去問を解くだけでは、応用が利いた問題に対処できない可能性があるためです。
宅建には、大きく以下の4分野に分かれています。
- 権利関係
- 宅建業法
- 法令上の制限
- 税・その他
宅建業法や法令上の制限といった暗記科目は過去問からの出題傾向が高いですが、まったく同じ文章で出題されるわけではありません。
問われる切り口や視点が変わったり、ひっかけ問題になったりすることが一般的です。
そのため、単に答えを丸暗記して数をこなすだけでは、対応できない問題に直面しやすく、高得点を狙うことは困難になります。
また、権利関係は試験範囲が広く、見慣れない問題が数多く出題されるため、過去問の知識だけでは範囲全体を網羅しきれません。
もちろん、条文の丸暗記に頼るだけだと高得点は狙いにくいため、関係図を描いたり、問題の趣旨や目的を深く理解したりする必要があります。
したがって、宅建の勉強をする際は最初にテキストで内容を理解し、その後に分野別と年度別の過去問2冊を解きまくるべきです。
おすすめの過去問
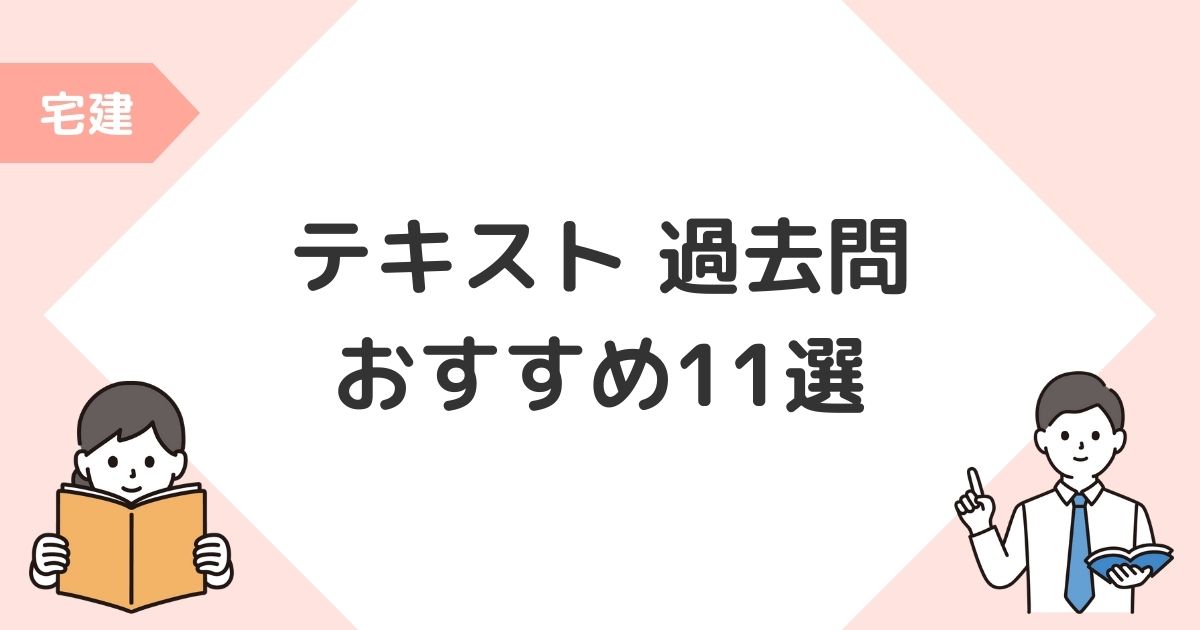
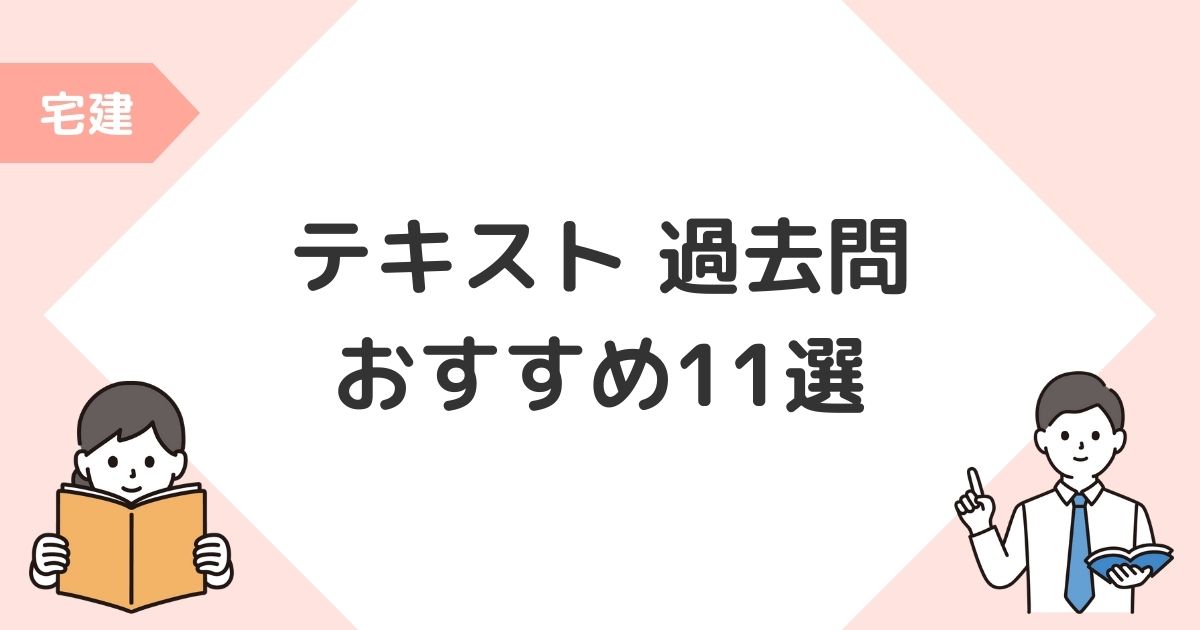
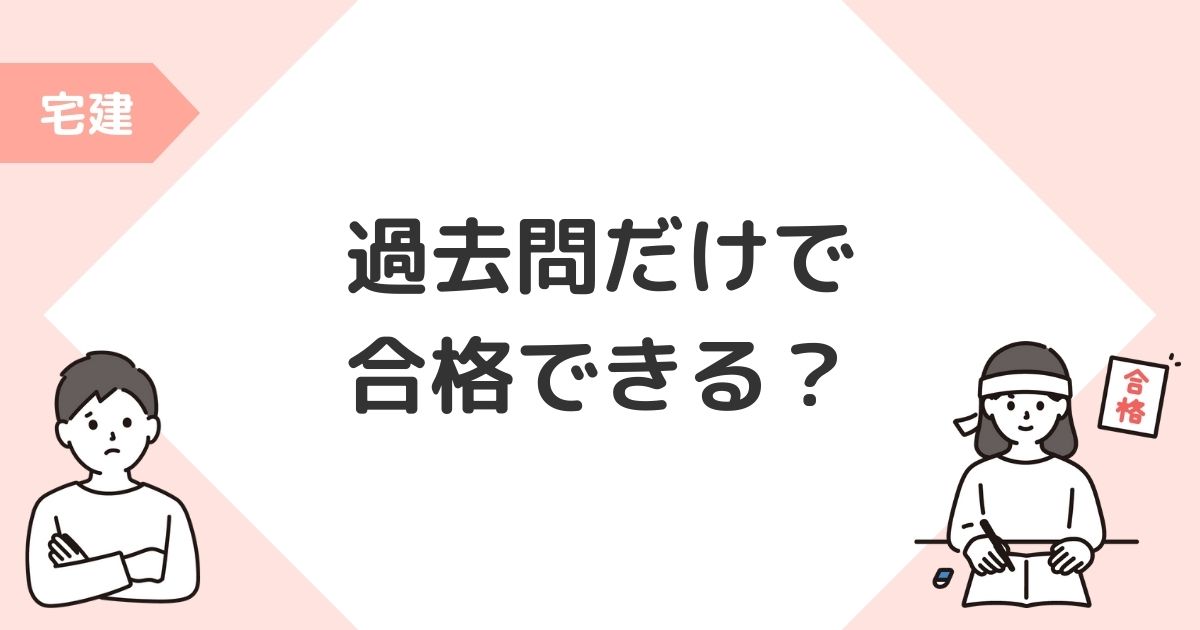
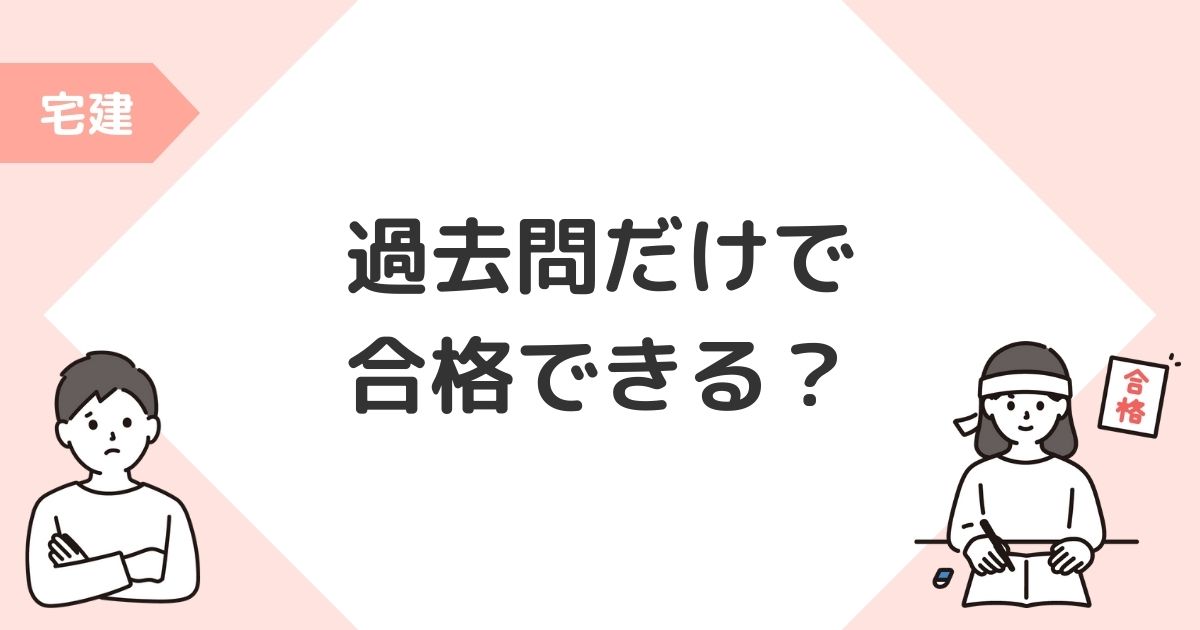
過去問を覚えてしまう方は予想問題集や模擬試験を活用しよう!
過去問を何度も解いていると、問題と解答を丸ごと覚えてしまい、本当に理解しているのか不安になることがあります。
もし、勉強時間に余裕があり過去問を覚えてしまったと感じるなら、予想問題集や模擬試験を活用しましょう。
過去の出題傾向を踏まえて、新たな視点や切り口で作成されているため、過去問にはない新しい問題に触れられ、真の実力を試すのに最適です。
また、試験本番に近い環境で模擬試験を受けることで、時間配分や精神的なプレッシャーに慣れることが可能です。
このように、過去問を覚えてしまう方は予想問題集や模擬試験を活用することで、どんな問題が出ても対応できる柔軟な思考力を身に付けられます。
おすすめの予想問題集
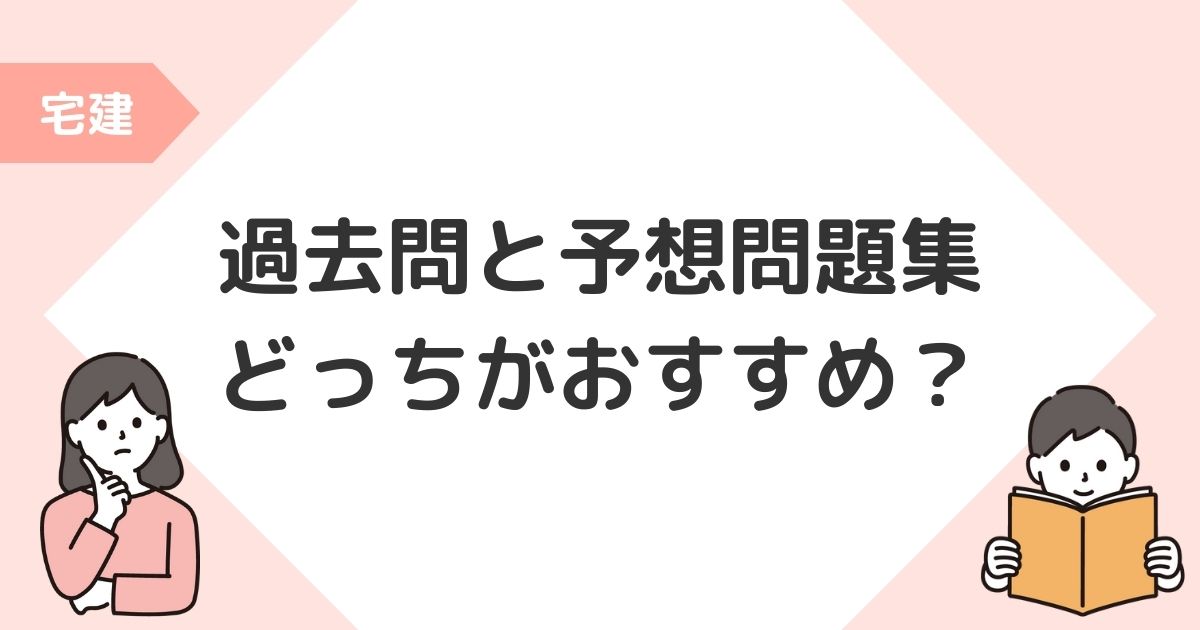
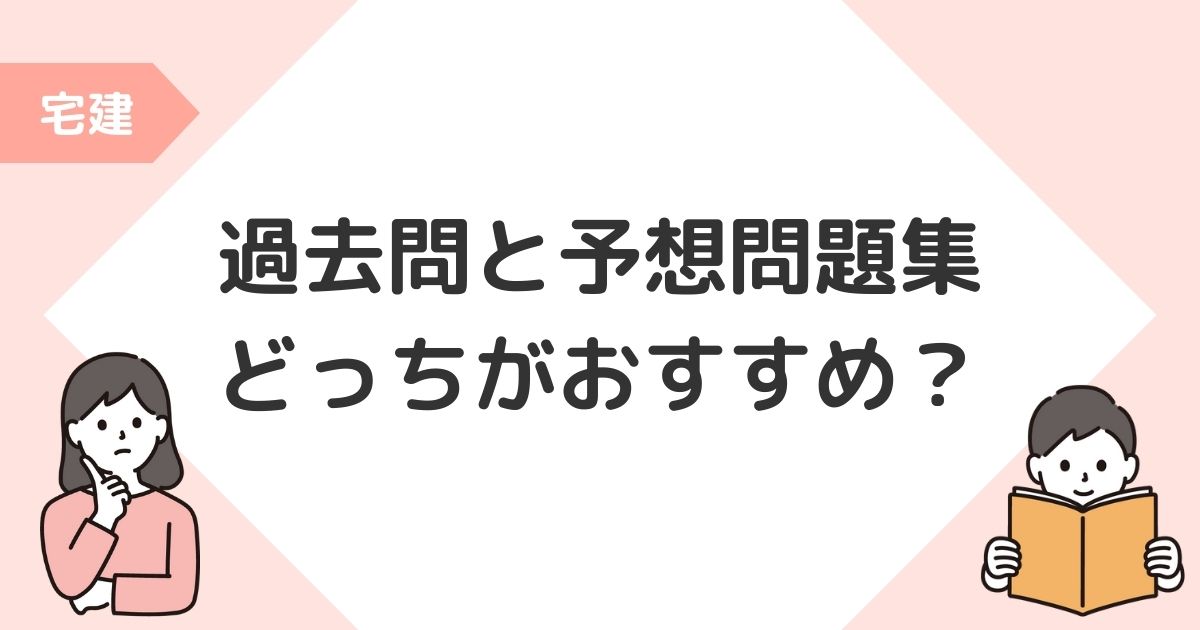
宅建の過去問だけを解きまくったのに落ちた人の特徴
宅建の勉強法として、過去問を解きまくることは有効ですが、それだけで合格できるほど本試験は甘くありません。
実際、過去問を徹底的に解いたにもかかわらず不合格になってしまう方には、いくつか共通する特徴があります。
ただ問題をこなすだけでは、本当の理解にはつながりません。
それぞれの特徴について、順を追って解説します。
テキスト(参考書)の内容を理解していない
過去問を解いているのに落ちてしまう人の最も大きな特徴の一つは、テキスト(参考書)の内容を根本的に理解していないことです。
中には、過去問を解き答え合わせをして、なんとなく正解した方や解説のみの知識しかない方もいるでしょう。
過去問はあくまで、知識の定着度を確認し、問題形式に慣れるための問題集です。
問題の背景にある法律の条文や制度の趣旨をテキストでしっかりと理解しないと、応用問題や文章が改変された問題、これまでとは異なる角度から問われた問題に対応できません。
こうした問題に対応するためにも、テキストを用いて問題の意図や背景を深く理解することが大事です。
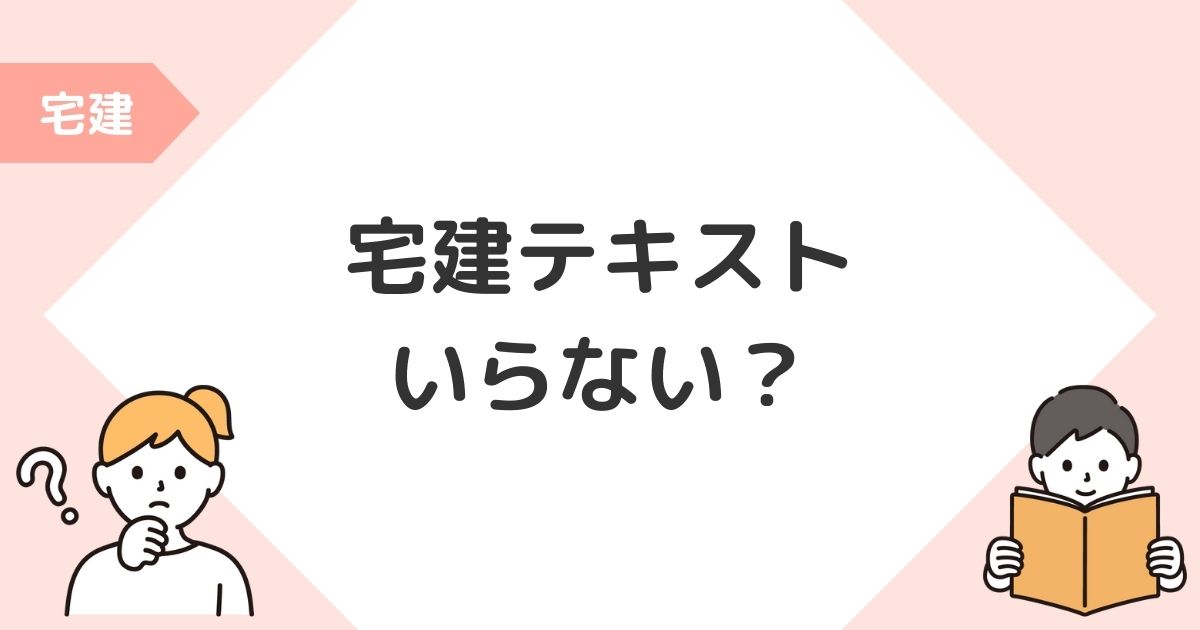
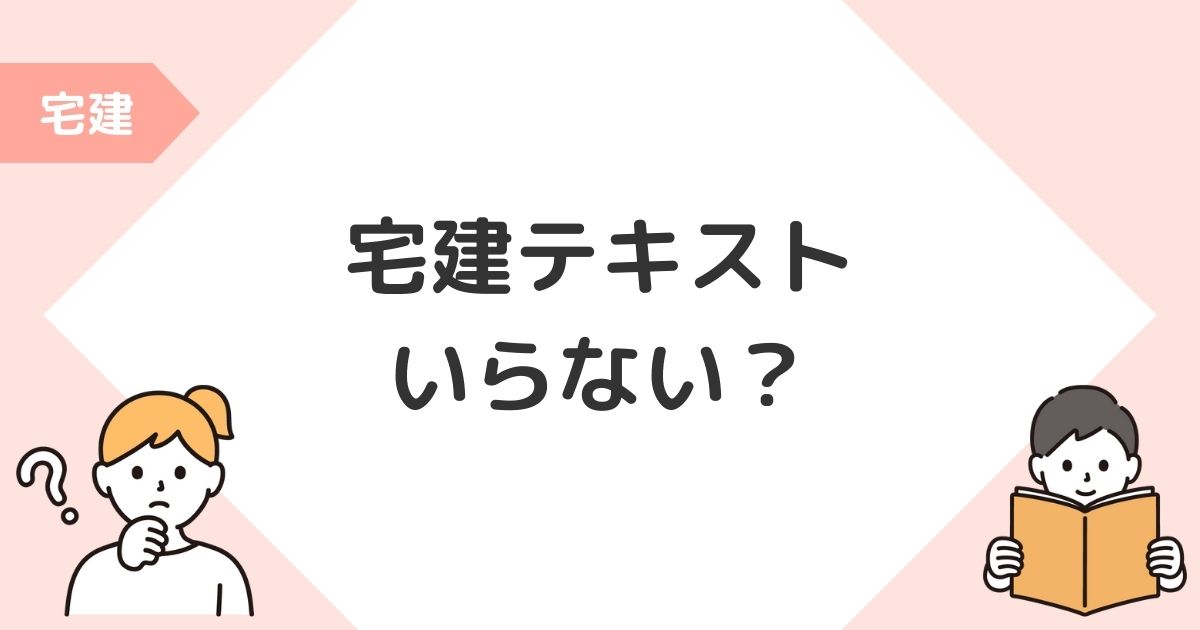
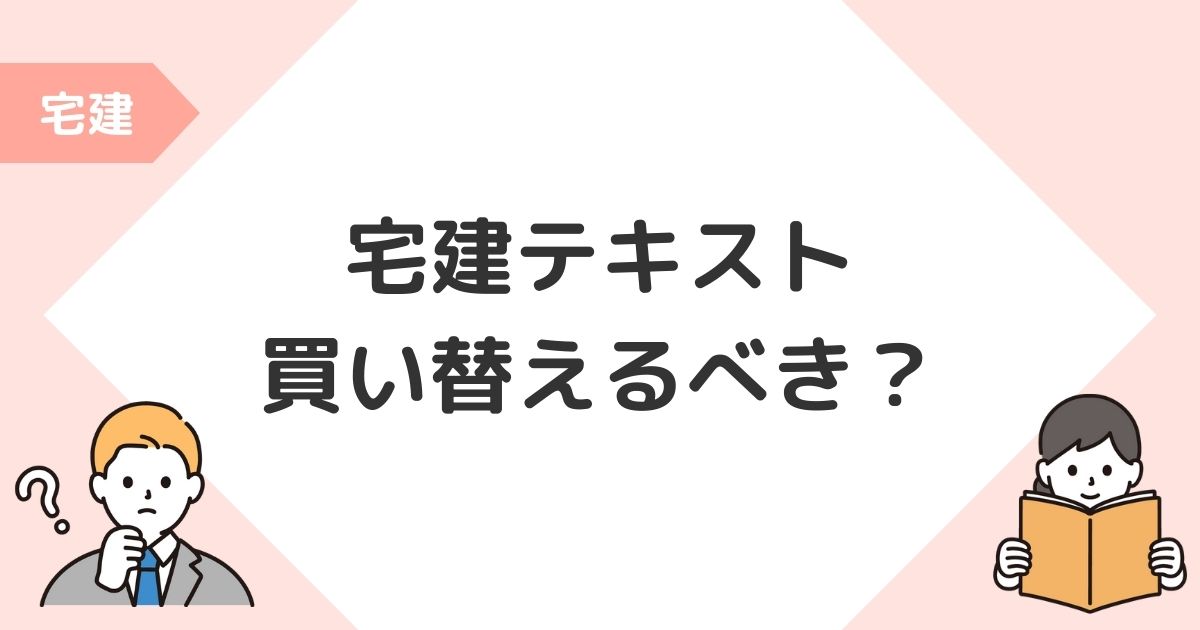
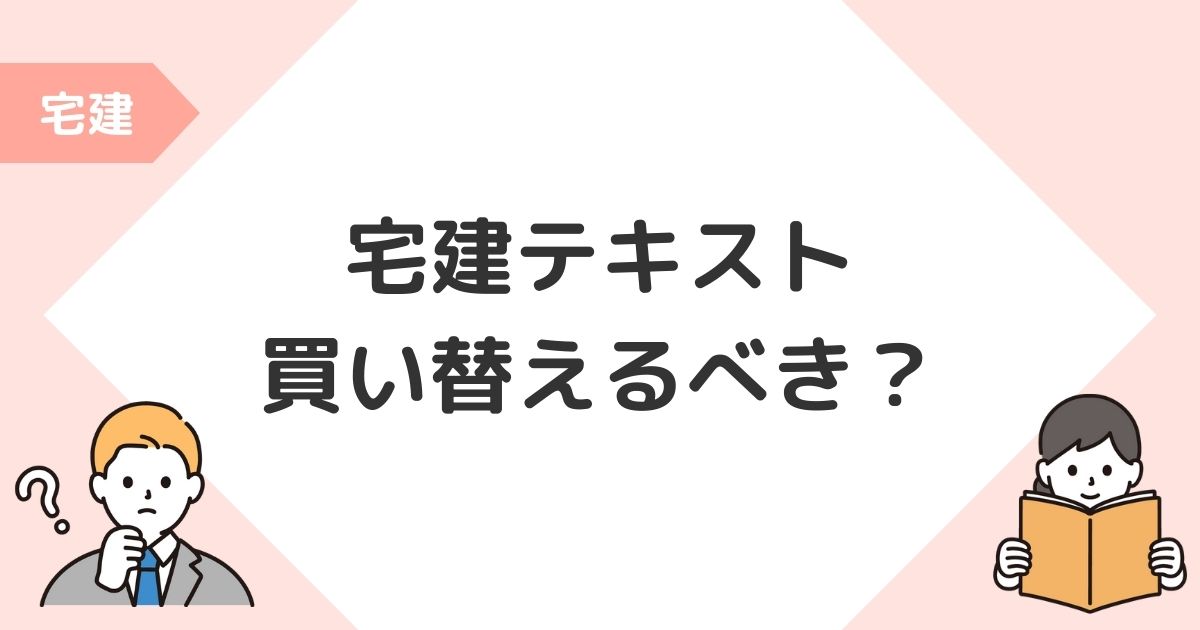
間違えた問題や運よく正解した問題の範囲を復習していない
過去問を解きっぱなしにして、間違えた問題や運よく正解した問題の範囲を十分に復習していないと、不合格に繋がるおそれがあります。
正解した問題はできたと安心しがちですが、たまたま運よく正解した場合は、再度似たような問題が出題されると間違える可能性があります。
間違えた問題はもちろん、前提知識があやふやで解いた問題も含めて、どの知識が不足していたのかを分析しましょう。
具体的には、該当する問題の論点に関連するテキストの箇所を再度読み込み、必要であればノートにまとめたり類似問題を解いてみたりと、徹底的に復習してください。
同じような間違いを二度としないよう、弱点と向き合う姿勢が合否を分けます。
問題を解く中でわからない点や曖昧な点が出てきたら、必ずテキストに戻り、その周辺知識も含めて掘り下げて理解を深めましょう。
本試験と似た環境下で解いていない
一般的な宅建試験では、2時間という限られた時間の中で、文量の多い50問を正確に読み解く能力が求められます。
そのため、本試験と似た環境下で実践練習をしていないと、不合格になる可能性があります。
たとえば、最初はともかく年度別過去問を解く際に以下のことを続けていると、本番で求められる時間配分の感覚や集中力を養えません。
- 途中で休憩を挟む
- 時間を計らずにだらだらと解く
- テキストや解説を見ながら解く
そのため、年度別過去問に慣れてきたら、必ず本番を想定して、以下の点を意識して取り組みましょう。
- 時間を計る:各問題にかけられる時間を意識し、ペース配分の練習をする
- 集中できる環境を整える:静かに集中できる場所を選び、本番と同じように中断せずに取り組む
- 解答用紙の記入練習をする:マークシート方式に慣れ、正確かつ迅速に解答を記入する練習を行う
これらの実践的な練習を積むことで、本番での緊張や焦りを軽減し、実力を最大限に発揮できるようになります。
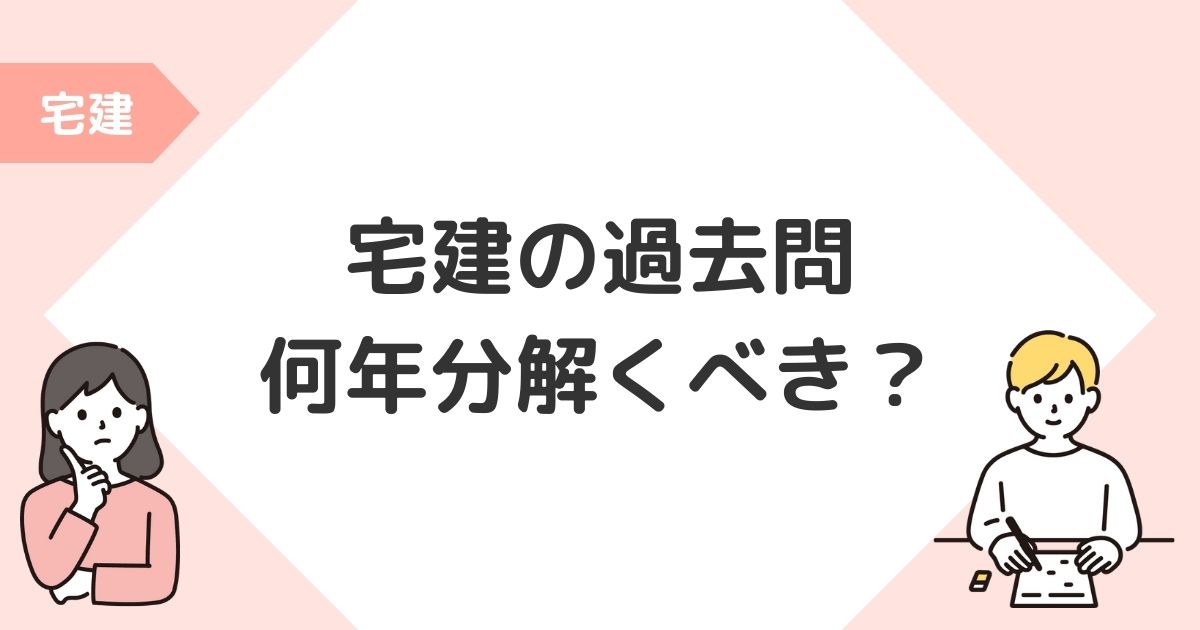
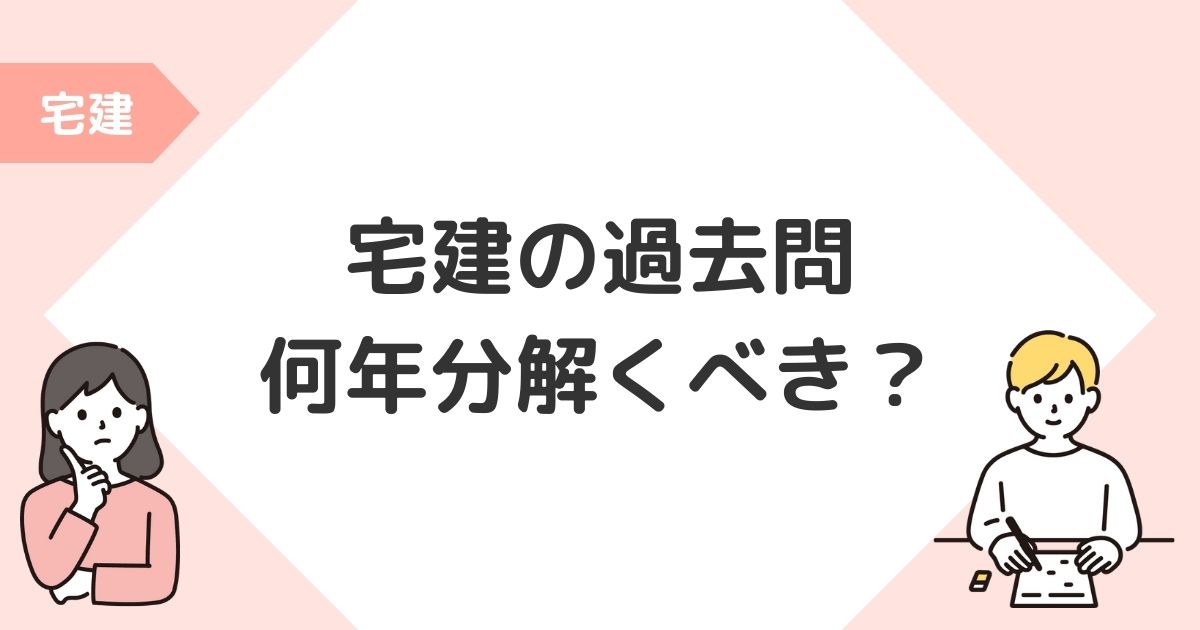
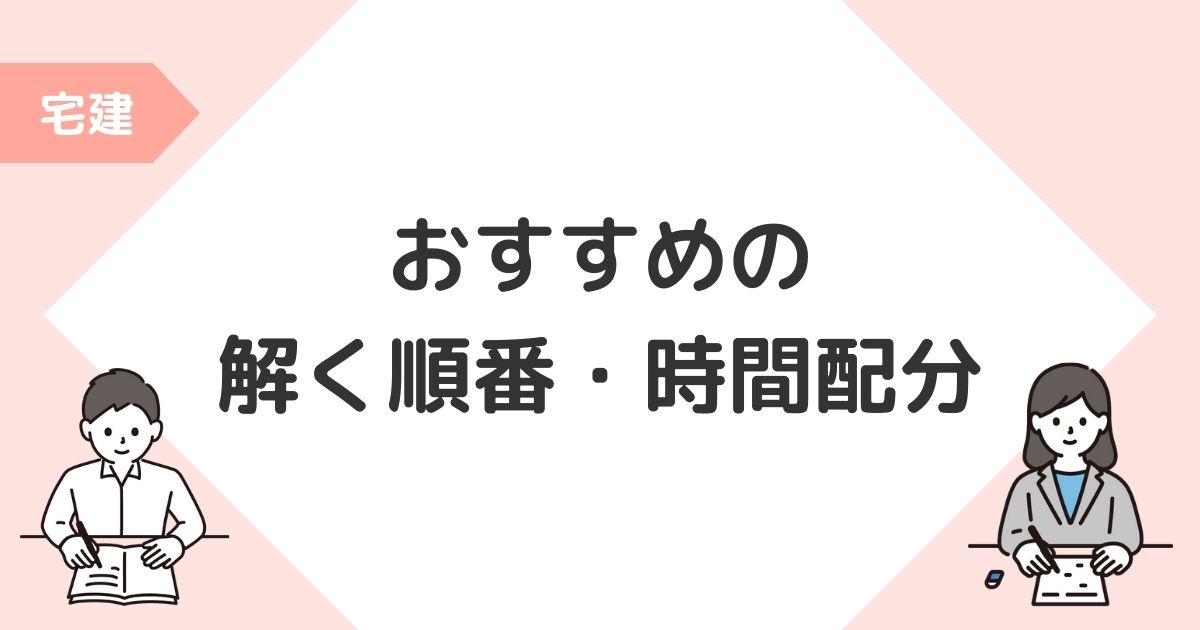
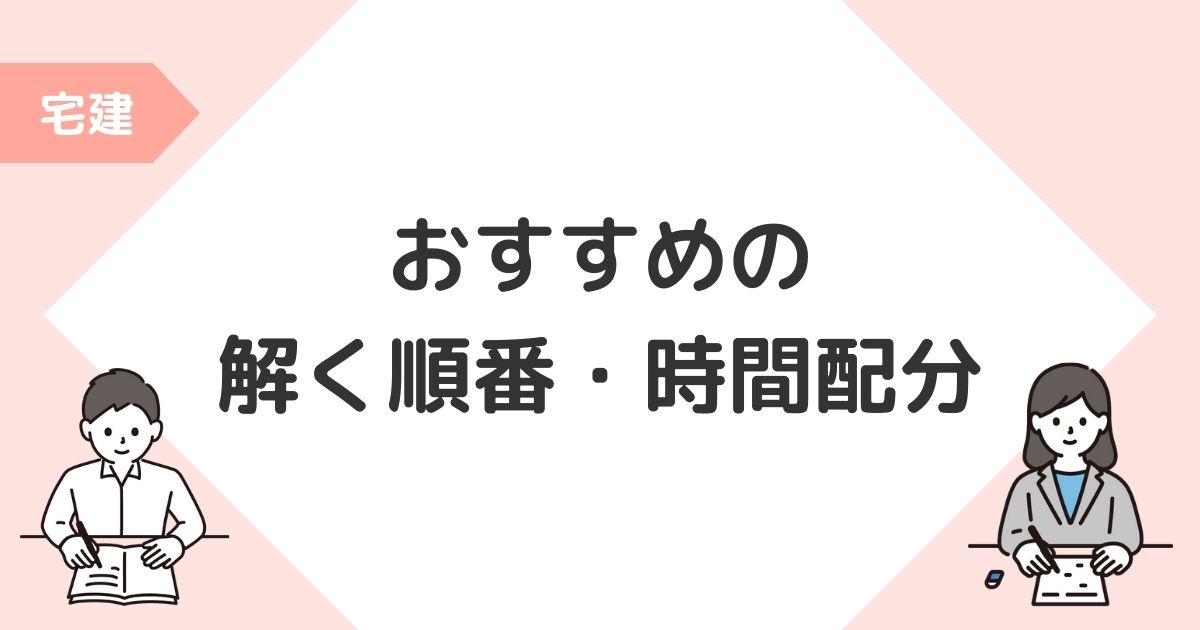


宅建は過去問だけを解きまくるべきだがテキストの復習や見直しも大事!
宅建試験において、過去問が合格への近道であることは間違いありません。
繰り返し問題を解くことで、出題傾向や問題形式に慣れ、実践的な対応力が身に付きます。
しかし、ただ闇雲に過去問を解くだけでは不十分です。
過去問で間違えた問題や解説を読んでも理解が曖昧な部分は、必ずテキスト(参考書)に戻って徹底的に復習し、知識の定着を図りましょう。
その際、問題の答えを覚えるだけでなく、その背景にある法律や制度を理解することが重要です。
また、本試験を想定した環境で時間を計って解く練習も欠かせません。
過去問を最大限に活用し、テキストでの基礎固めと復習を怠らないことが、宅建試験の合格を確実なものにする鍵となります。