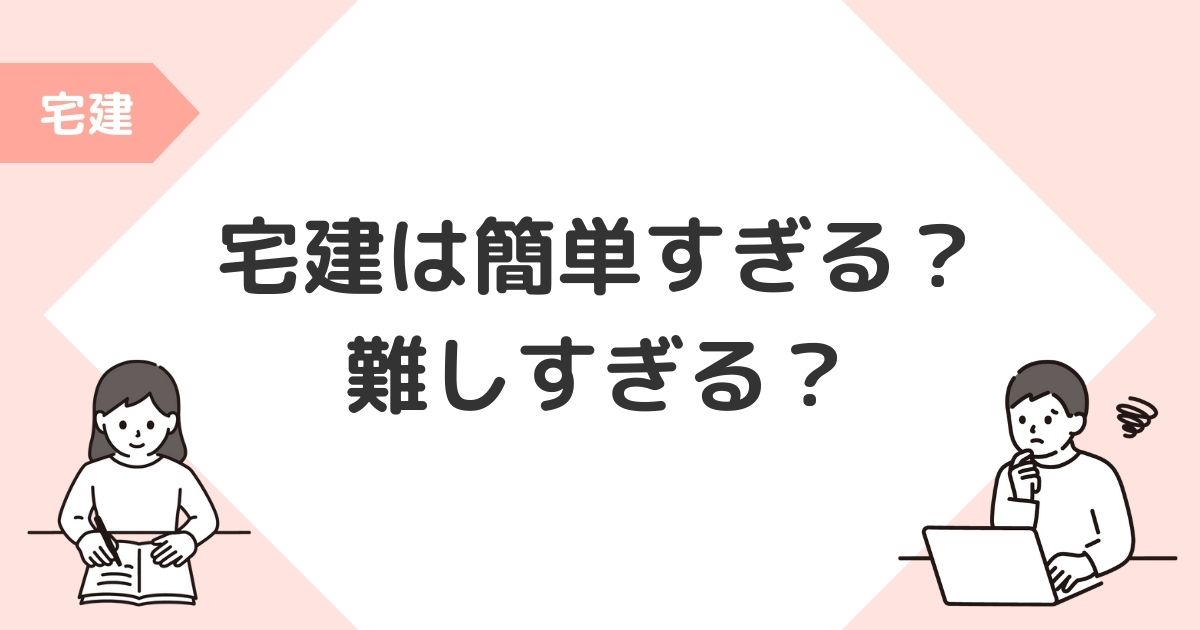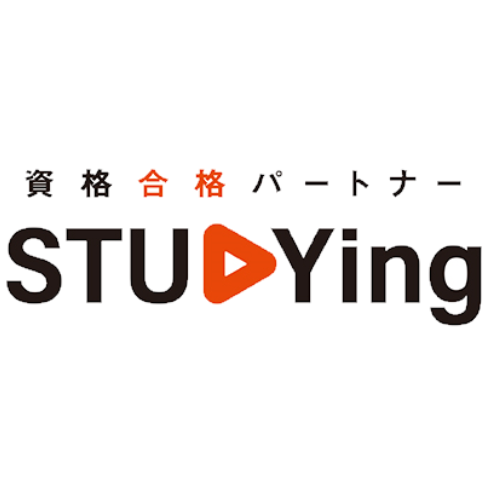宅建は簡単すぎるのか、それとも難しすぎるのか、どっちなのか疑問に思っていませんか?
 ふぁも
ふぁも私は当初、宅建は難しいイメージがありました。
そこで本記事では、宅建は簡単すぎる?難しすぎる?に対する回答と、そう感じる理由について紹介します。
最後まで読むことで、おおよその難易度がわかり、勉強戦略に沿って学習を始められるはずです。
宅建の難易度について気になっている方は必見です。
「独学の方」や「通信講座にしようか迷っている方」にも朗報!
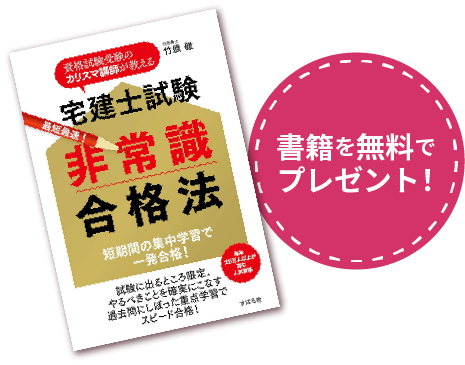
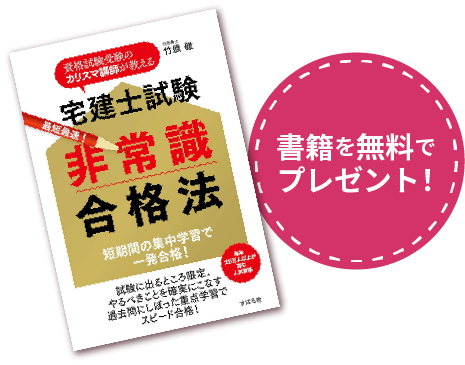
今ならクレアールでは「宅建士試験 非常識合格法」が無料プレゼント中です!
市販で買うと1,650円する書籍が、期間限定で「0円」でもらえます。
- 最短最速で合格が狙える!
- 試験の出題傾向と対策が知れる!
- 合格に必要なポイントだけをおさえた学習法がわかる!
最小努力で合格するコツや本試験直前までの過ごし方など、宅建受験生には必要不可欠な情報が知れます。
いつ終わるか分からないので、合格を目指している方は今すぐにゲットしましょう!
>>「宅建士試験 非常識合格法」をゲットする!
※早い方だと登録は1分で入力完了します!
私も実際に取り寄せましたが、その後のしつこい勧誘・強引な押し売りは一切ありませんでした。
- 宅建やFP2級をはじめ数多くの資格を保有
- Webライターで月20万円超稼ぐ
- 塾講師として1年半・小中高20人以上の生徒を指導


ふぁも
宅建は簡単すぎる?難しすぎる?
いろいろと調べてみると、宅建は簡単すぎるという声もあれば、難しすぎるという意見もあります。
ただし、宅建の勉強を始めて自ら体感しないと、どのくらいの難易度だかわかりません。
【結論】極端に簡単・難しいわけではない
宅建は極端に簡単・難しいというわけではありません。
なぜなら、「すべて」の資格で比べると、宅建の難易度は真ん中〜やや難しいあたりになるためです。
実際問題、何の資格と比べるかによって、難易度が大きく異なります。
たとえば、「法律資格」だけで考えると、宅建の難易度は易しい方に分類されます。
合格率について、宅建は15〜17%程度に対して、他の法律資格は全体的に合格率が1桁のものが多いです。
また、合格に必要な勉強時間についても、ほとんどの法律資格では1,000時間を超えますが、宅建は300〜500時間で済みます。



勉強時間は人によって異なるので、あくまでも目安です。
しかし、「すべて」の資格で比べると、難易度は異なるので注意が必要です。
「すべて」の中には、2人に1人以上が取れる簡単な資格も含まれているため、宅建の難易度は全体で真ん中〜やや難しいあたりになります。
このように、法律経験者が法律資格の中で最も易しいといわれる宅建を受けると、簡単すぎると感じるかもしれません。
ただし、法律初学者が受けると難しすぎると感じやすい傾向です。
今までの勉強量や経験量によって変わる
宅建の難易度は、今までの勉強量や経験量によって異なります。
たとえば、そもそも最近勉強をしていない人が、いきなり勉強を始めると、どの内容でも難しすぎると感じやすいです。
一方、受験勉強を経験し毎日のように勉強をした人は、難しい問題が出ても対処する方法がわかっているため、少なくとも難しすぎるとは感じにくいはずです。



受験勉強を経験したからといって、挫折なく宅建の勉強ができるとは限りません。
私は大学受験後に宅建の勉強をしましたが、一度挫折したことがあります。
また、不動産業に従事している方は、不動産に関する法律について詳しい傾向にあります。
そのため、法律初学者と比べると多くの知識や実務経験があるため、内容の理解しやすいです。
このように、今までの勉強量や経験量によって、難易度の感じ方は大きく異なるのです。



簡単すぎると感じる方は、本番でミスをしないようにしましょう。
一方、難しすぎると感じる方は、マインド・努力次第で乗り越えられますよ!
宅建は簡単すぎると感じる理由
ここからは、宅建が簡単すぎる・難しすぎると感じる理由について詳しく解説します。
最初に、宅建は簡単すぎると感じる理由として、以下のことが挙げられます。
法律の学習経験者にとっては、簡単すぎると感じるかもしれません。
必要な勉強時間が比較的短くて済む
宅建合格に必要な勉強時間は、一般的に300〜500時間程度といわれています。
そのため、宅建の勉強開始時期は、試験日の半年前から始める人が多い傾向です。
ただし、他の法律資格と比べると大きく勉強時間が増えることになります。
たとえば、司法試験に合格するのに一般に3000〜8000時間と、宅建と比べると10倍以上の勉強時間が必要になります。
そのため、宅建は他の法律資格と比べると勉強時間が少なく、簡単すぎるといわれます。
他の法律資格と比べて合格率が高い・難易度が低い
宅建試験は他の法律資格と比べると、合格率が高く難易度が低い傾向にあります。
実際に他の法律資格と比べると、合格率が高いことがわかります。
| 資格 | 合格率 |
|---|---|
| 宅建 | 15%〜17% |
| 行政書士 | 10%〜12% |
| 弁理士 | 6%〜10% |
| 司法書士 | 4%〜5% |
| 中小企業診断士 | 5%〜7% |
| 社労士 | 5%〜6% |
| 司法試験(予備試験) | 3%〜4% |
合格率が高いということは、その分多くの人が合格でき、難易度が下がる傾向にあります。
これにより、他の法律資格と比べて宅建が簡単すぎるという声が出るようです。
四肢択一のマークシート形式で解答する
宅建試験では、すべての問題において、「四肢択一」のマークシート形式で出題され、記述はありません。
そのため、もしわからない問題があっても、勘で解けば正解になる可能性があります。
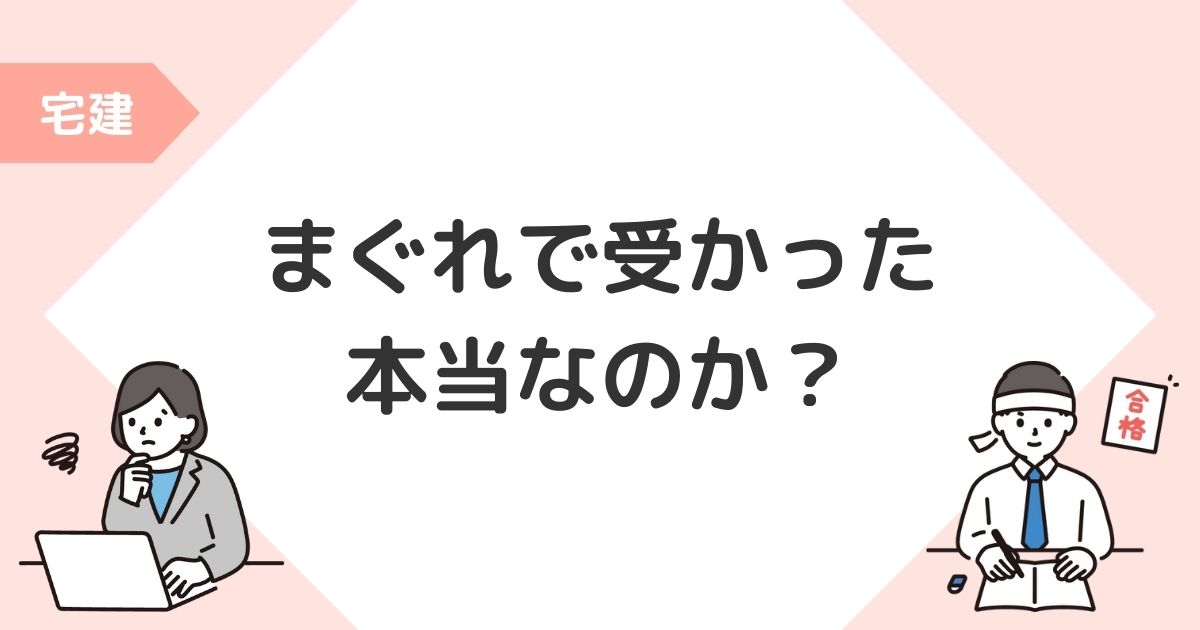
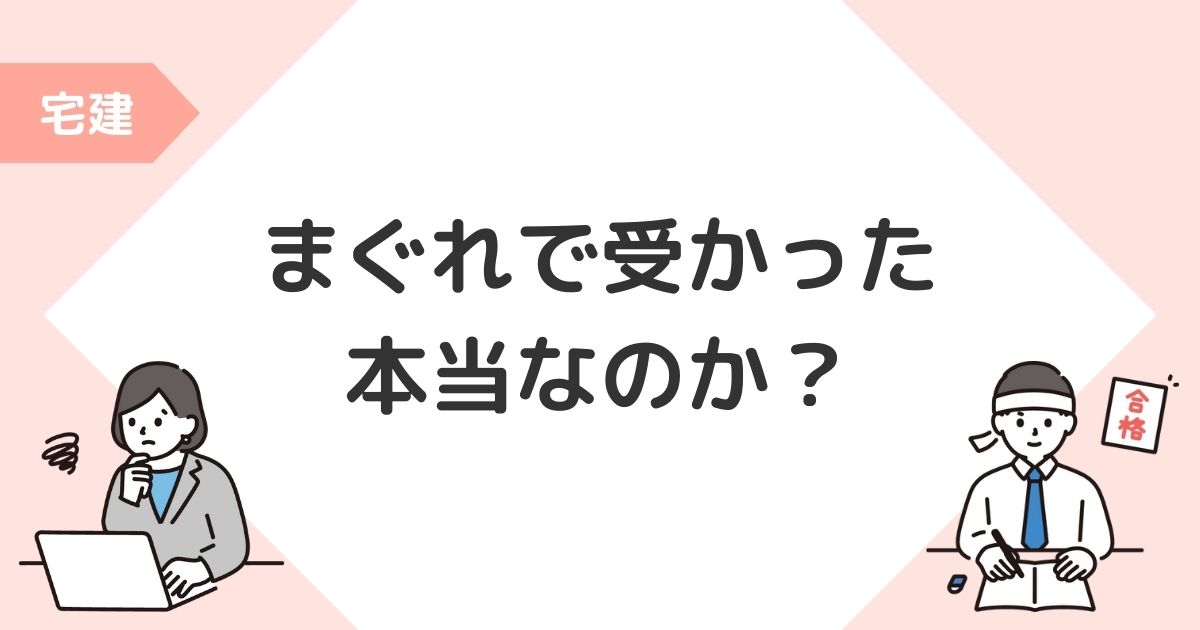
たとえば、行政書士試験では、同じマークシート形式でも選択肢が1つ多い「五肢択一」のため、その分正解の可能性が下がります。
このように、マークシート形式の出題で選択肢が少ないため、簡単そうに感じやすいです。


宅建は難しすぎると感じる理由
一方、宅建は難しすぎると感じる理由として、以下の通りです。
法律初学者にとって、勉強のハードルが高い可能性がありますが、マインドと努力次第では乗り越えられるはずです。
試験範囲が想像以上に広い
宅建試験では、主に以下の4つの分野から幅広く出題されます。
- 権利関係
- 宅建業法
- 法令上の制限
- 税・その他
特に権利関係の民法は、試験範囲が広く難易度が高いため、攻略するのに時間がかかります。
このように、不動産に関する勉強のみならず、民法をはじめ、さまざまな分野の勉強が必要になるため、難しすぎると感じやすいです。
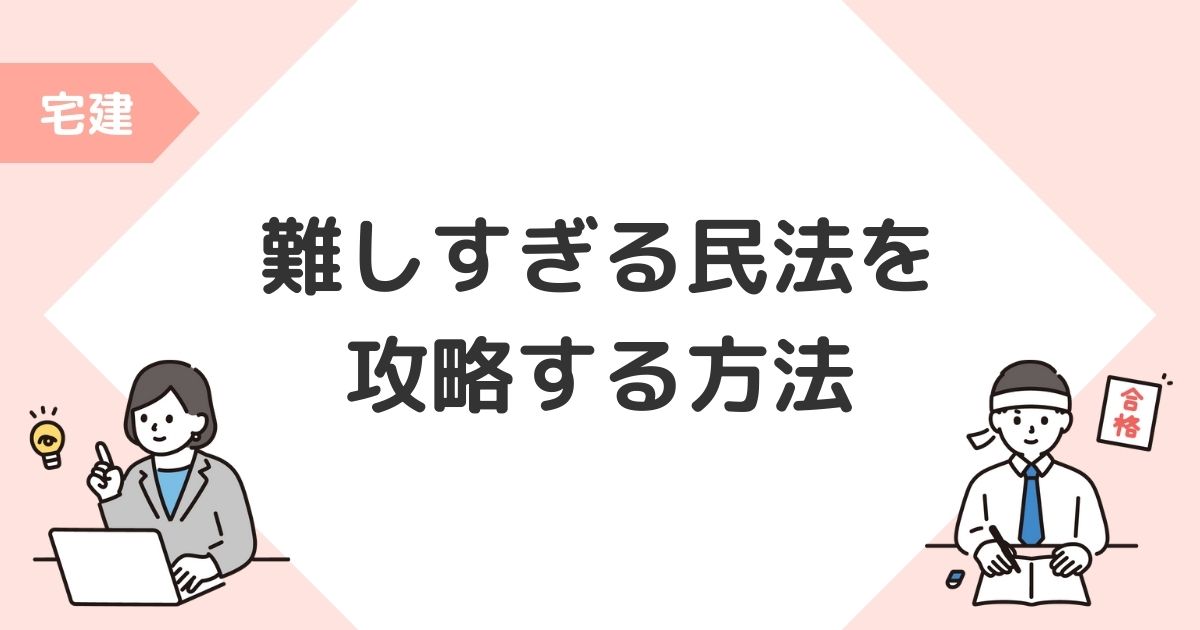
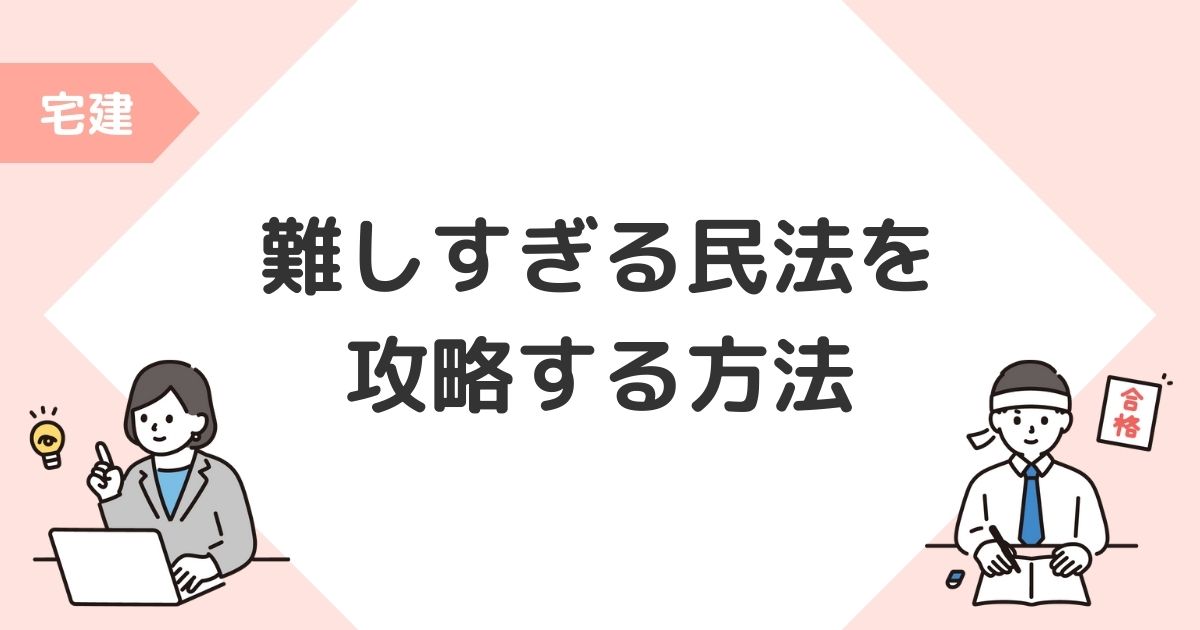
難易度の割に問題が難しい
宅建は法律資格の中で易しい方ですが、それでも難しい問題が多く出題されます。
その中でも、民法は最も難しい分野といわれており、過去問と同じような問題が出題されにくいです。
また、たとえ簡単な分野であっても、出題形式で難しくしてあります。
たとえば、適切・不適切な選択肢を数える「個数問題」は、あいまいな知識では正解できません。
そのため、どの分野でもはっきりとした知識を備えることが大事です。
ここで、試験範囲が広いことを踏まえると、すべての分野を理解するのは難しすぎるという声もあります。
法律用語を理解するが難しい
宅建では、不動産に関する用語だけではなく、民法をはじめとした法律も学ぶ必要があります。
たとえば、以下のような法律用語は法律初学者からすると、何を言っているのかわからないかと思います。
宅建に出る主な法律用語
- 善意・悪意
- 無過失・重過失
- 対抗できる・できない
- 債務不履行
- 追完請求
- 不法行為



私も初めて法律用語を見たとき、さっぱりわかりませんでした。
このように、日常では馴染みのない法律用語が多いあまり、難しすぎると感じる傾向です。



宅建を難しくしている原因は、何回も強調していますが「民法」です。
全体の20%を占めているので、いかに民法を攻略するかが大事になります。
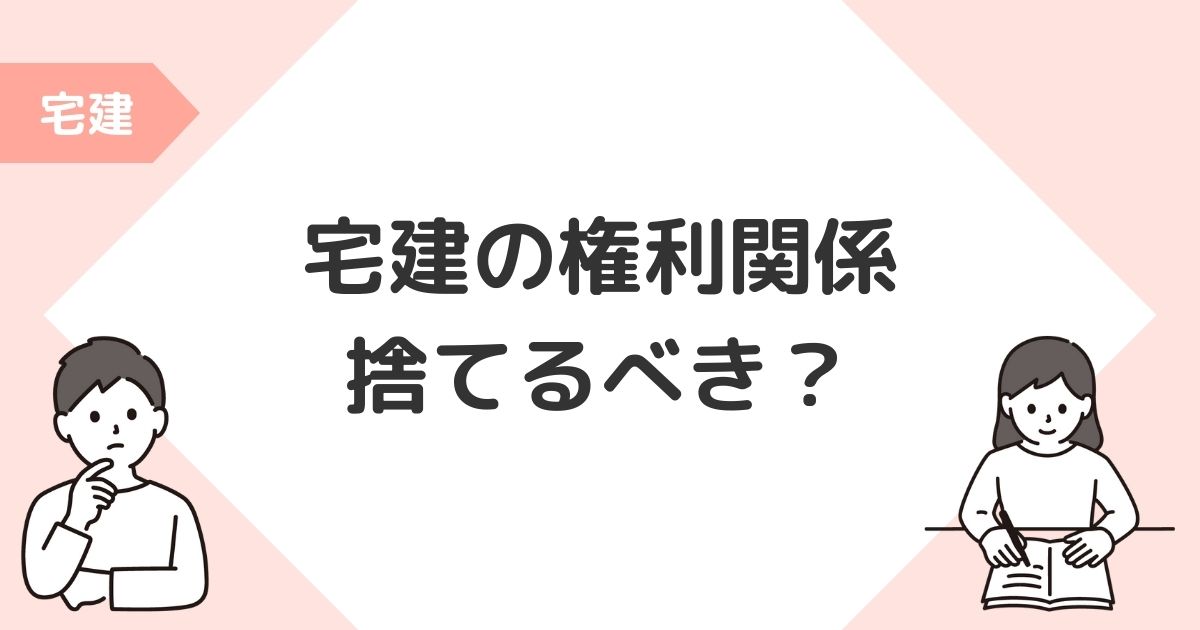
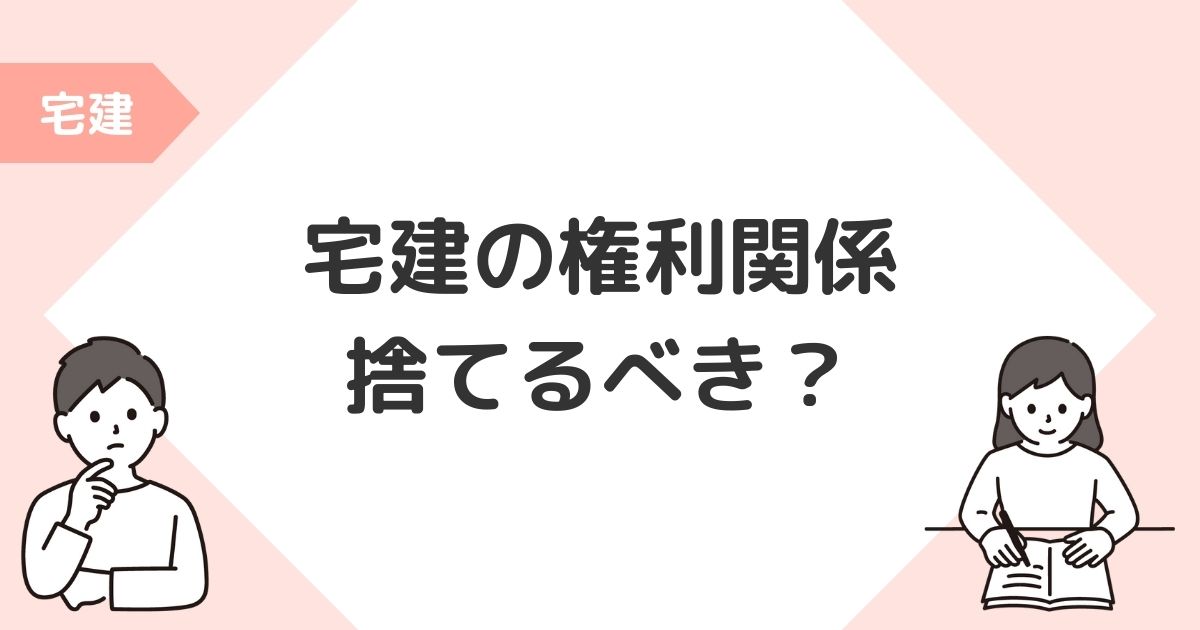
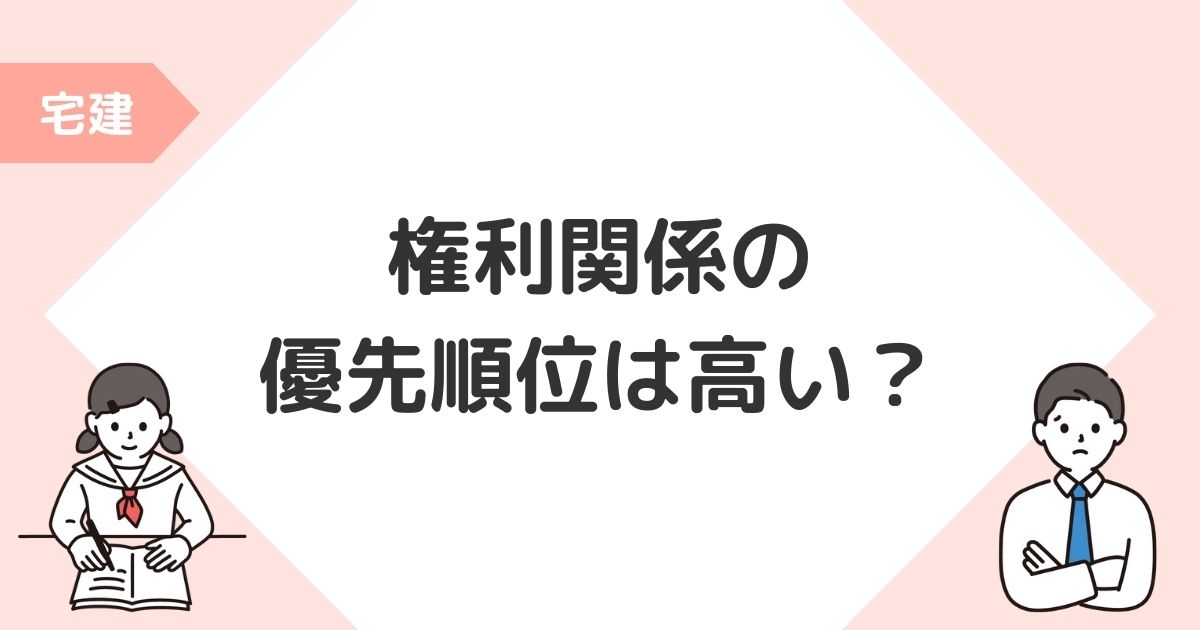
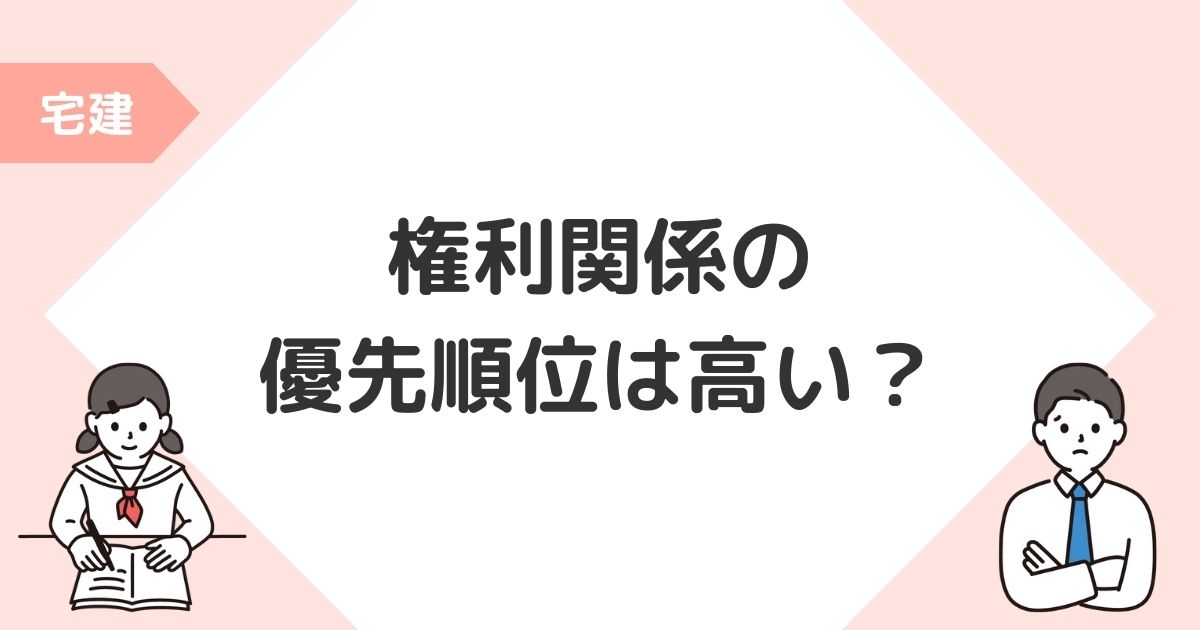
宅建は簡単すぎる・難しすぎると感じる方が実践すべき勉強戦略
宅建は簡単すぎると思っている方も、難しすぎると感じている方も、まずは以下の勉強戦略に沿って、下準備を進めることが大事です。
1つずつステップを踏めば、良いスタートダッシュが切れるはずです!
宅建試験の概要・勉強法を把握する
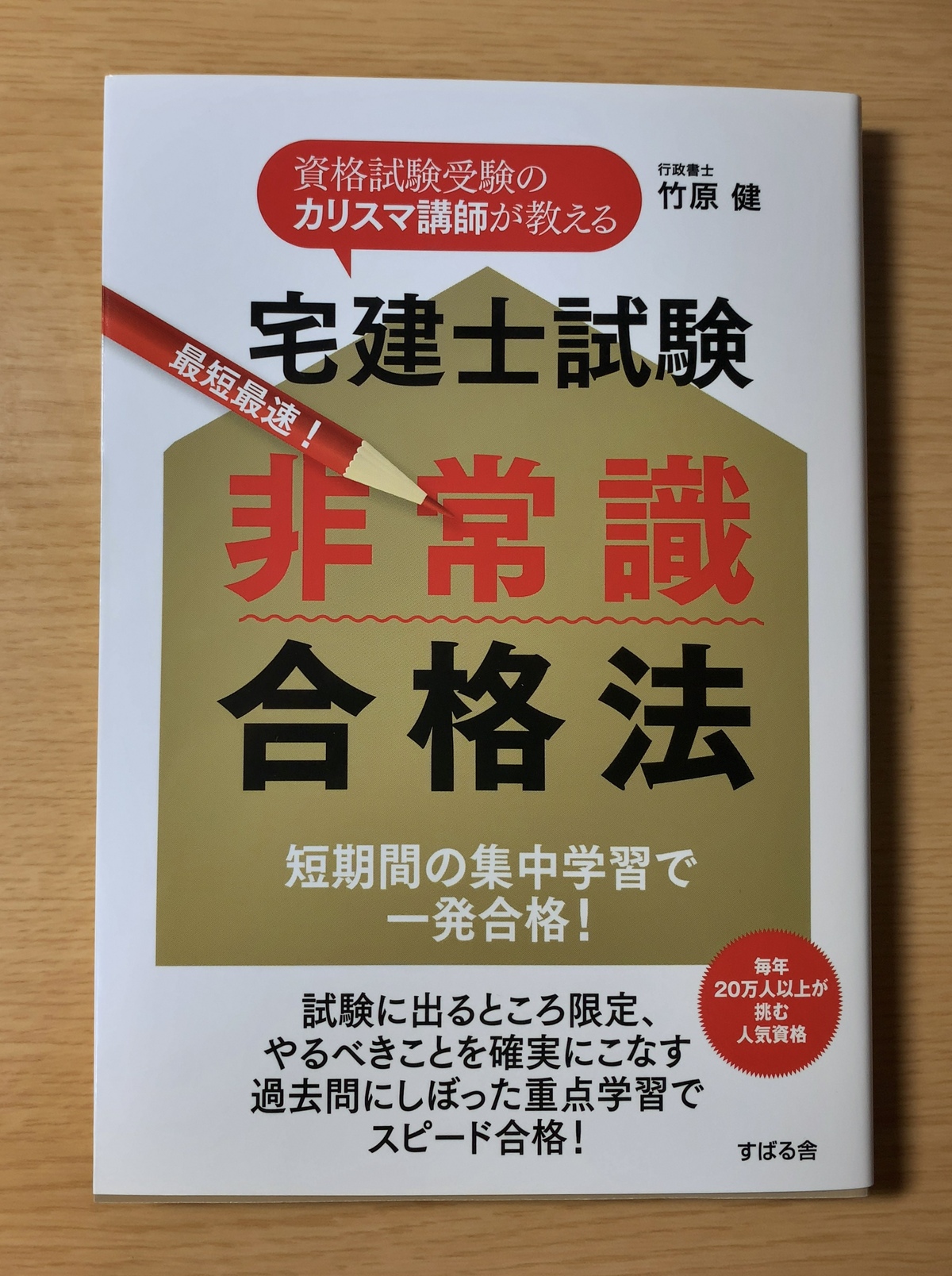
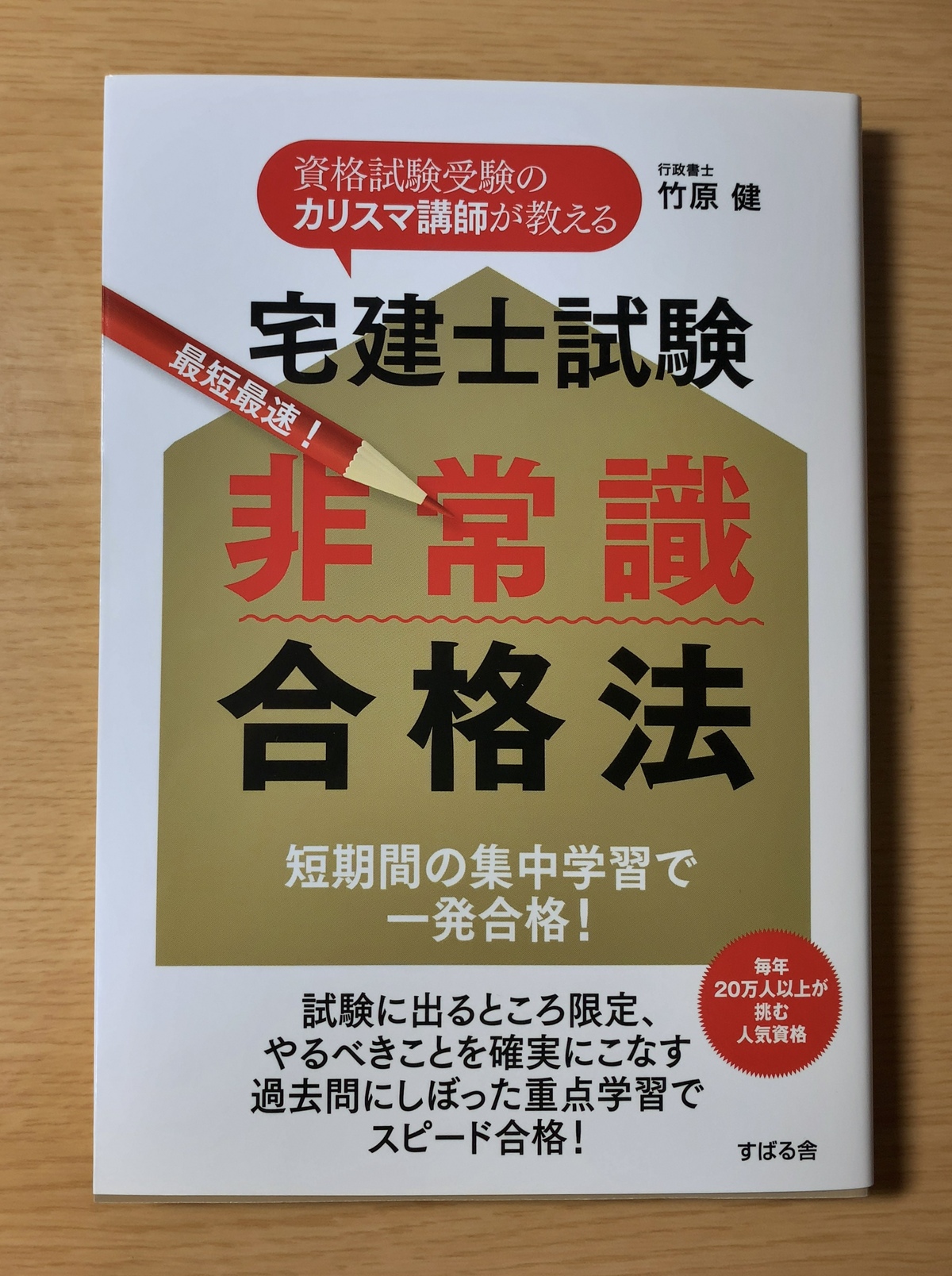
まずは宅建試験の概要や勉強法を詳しく知ることが大事です。
ネットで情報収集するのも良いですが、効率面を考えると無料でもらえるクレアールの書籍「非常識合格法」を活用することをおすすめします。



ネットでの情報収集は想像以上にかかります。
私は情報を集めるだけで数日はかかりました…
非常識合格法を読むことで、以下のことが分かります。
- 宅建試験の概要・特徴
- 試験の出題傾向
- 過去問による学習方法
- 試験直前や前日のアドバイス
- 試験に出る箇所・要点を絞った学習範囲
これにより、無駄な労力をかけることなく、合格を目指すことが可能です。



私は権利関係に深入りしてしまい一度挫折した経験があります。
非常識合格法があれば、勉強を継続できたかもしれません。
本書籍をもらうためには、講座を受ける必要はなく「無料登録をするだけ」です。
しつこい勧誘はないので、ぜひこの機会にゲットしましょう!
\早い者勝ち!カンタン1分で入力完了/
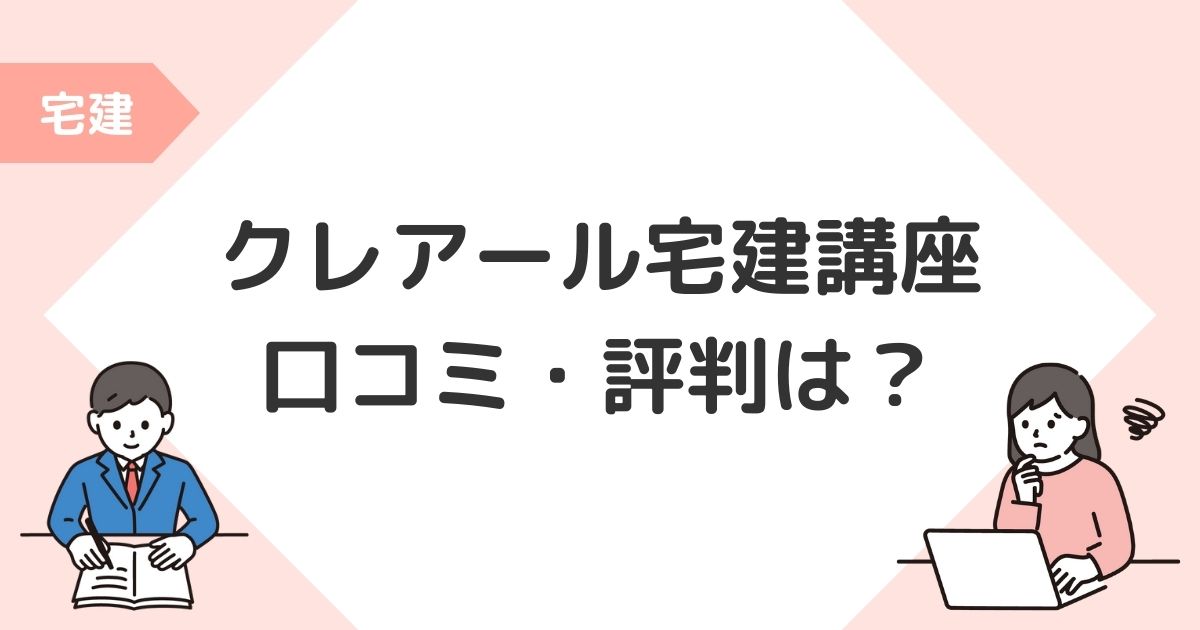
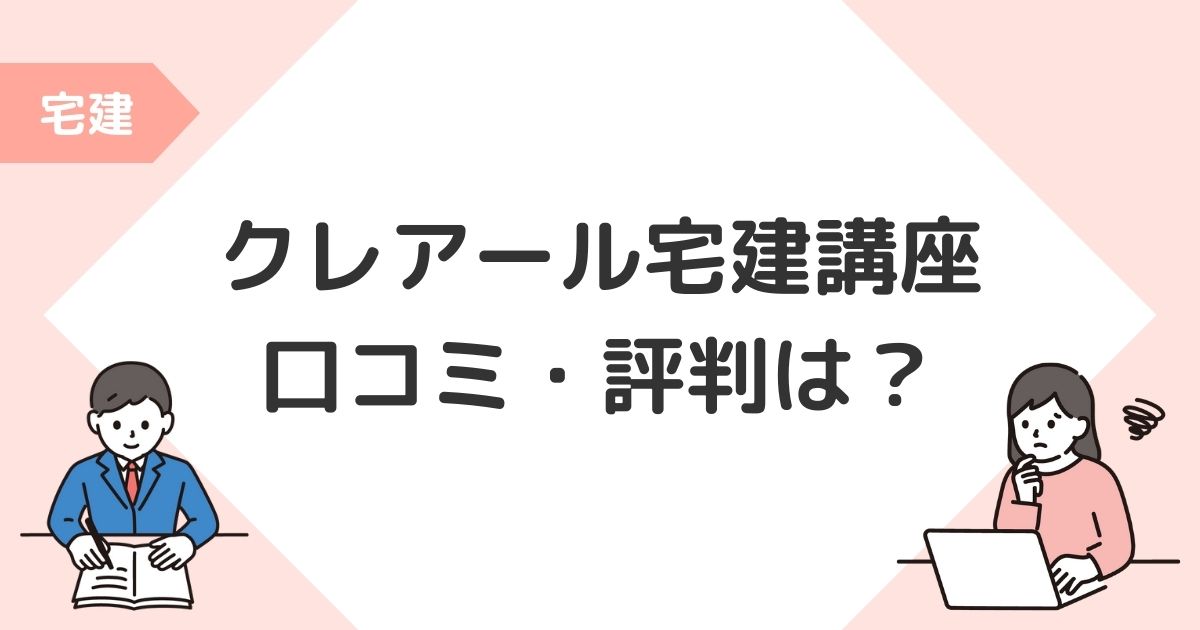
勉強期間を多めに確保する
勉強期間を確保するのは当たり前だと思いますが、できていない方も少なからずいます。
実際に宅建に落ちてしまった方の多くは、勉強期間を十分に確保できていないのが原因です。
だからといって、勉強が嫌いな方や長い間していない方がいきなり勉強を始めると、無理をしてすぐに挫折してしまう恐れがあります。
挫折しないためにも、周りの勉強期間や勉強時間に流されず、余裕を持って自分のペースで勉強するのが大事です。



少しずつ勉強を始めて、慣れてきたら勉強時間を増やしましょう!
また仕事や家事に追われている方は、1日に勉強できる時間が限られるため、勉強期間は多めに確保しましょう。
おすすめの開始タイミングは「2月中旬頃」です。
1日2時間勉強をすれば、10月中旬にある試験日に500時間達成できる計算になります。



もちろん、人によって勉強時間や勉強に確保できる時間が異なる以上、勉強期間は一概には決められません。
自分のライフスタイルや経験に合わせて、自由にカスタマイズしてくださいね!
詳しくはこちらで計算していますので、参考にしてください。
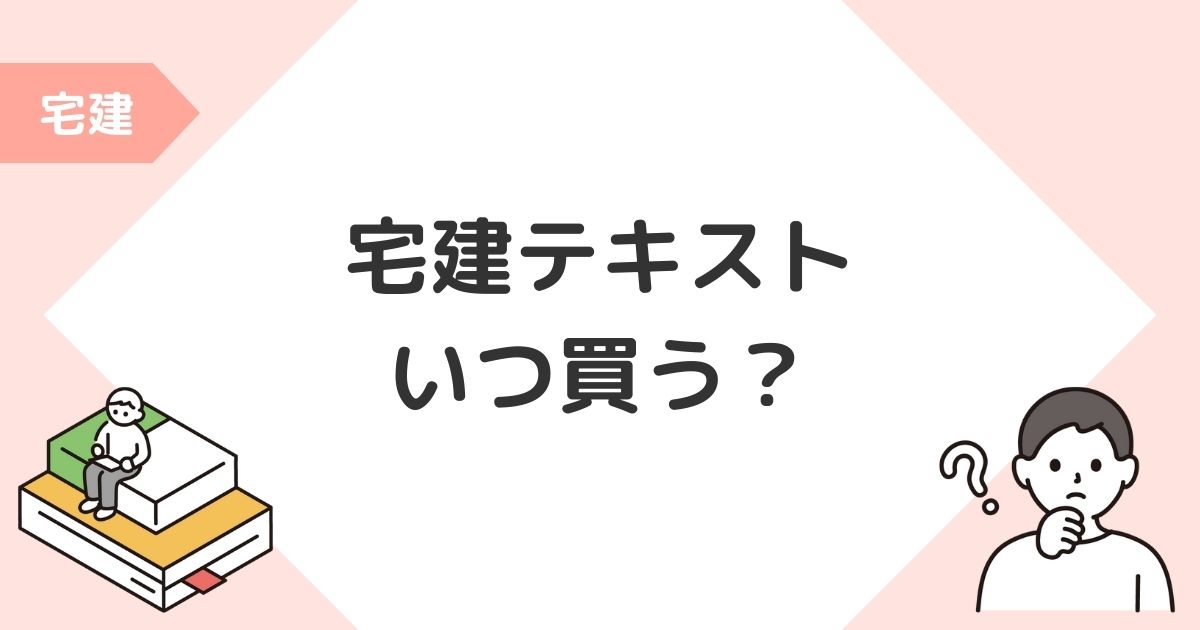
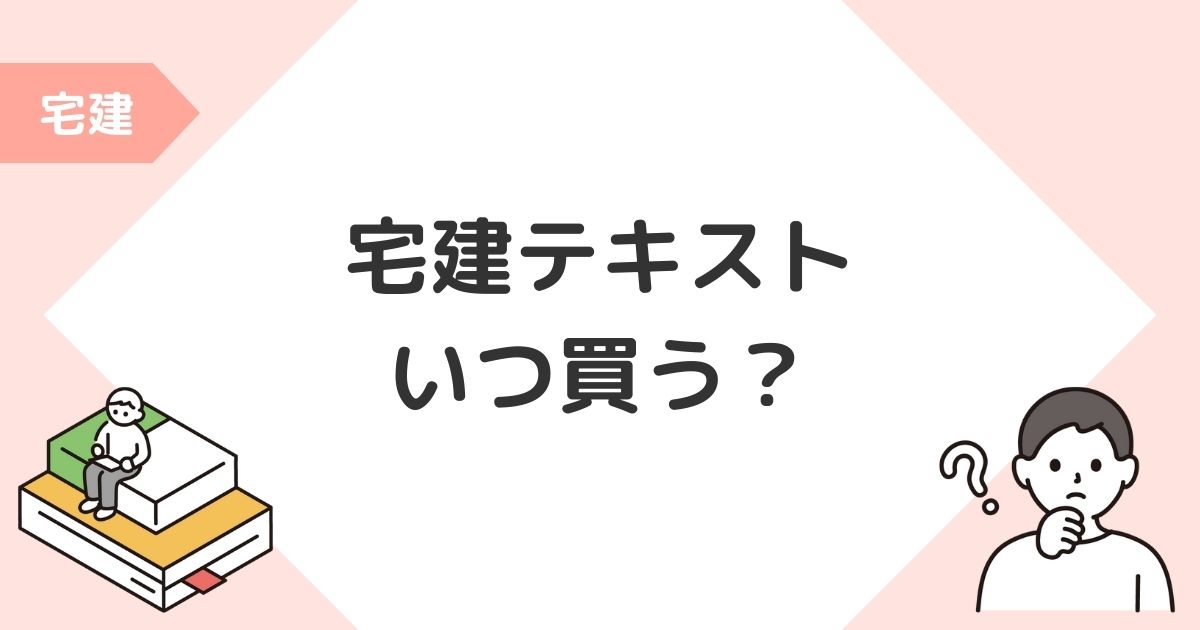
3つの学習スタイルから選択する
宅建試験の勉強には、大きく3種類の学習スタイルがあります。
| 学習スタイル | 特徴 | 費用目安 |
|---|---|---|
| 独学 | お金がかからない 自分のペースで勉強できる 自らスケジュール管理する必要がある | 1万円以内 |
| 通信講座 | 効率良く学べる 自宅から好きな時間で学習できる すぐに質問できない | 6万円前後 |
| 通学講座 | 講師と対面で学べる 他の受験生と一緒に勉強できる お金がかかる | 10万円前後 |
どの勉強法を選ぶかは人によって異なるので、それぞれの特徴を把握した上で選択しましょう。
なお、基本的には独学か通信講座かのいずれかを選ぶことになります。



安さにこだわるのなら独学一択です。
テキストや通信講座選びに悩んでいる方は、以下の記事を参考にしてください。
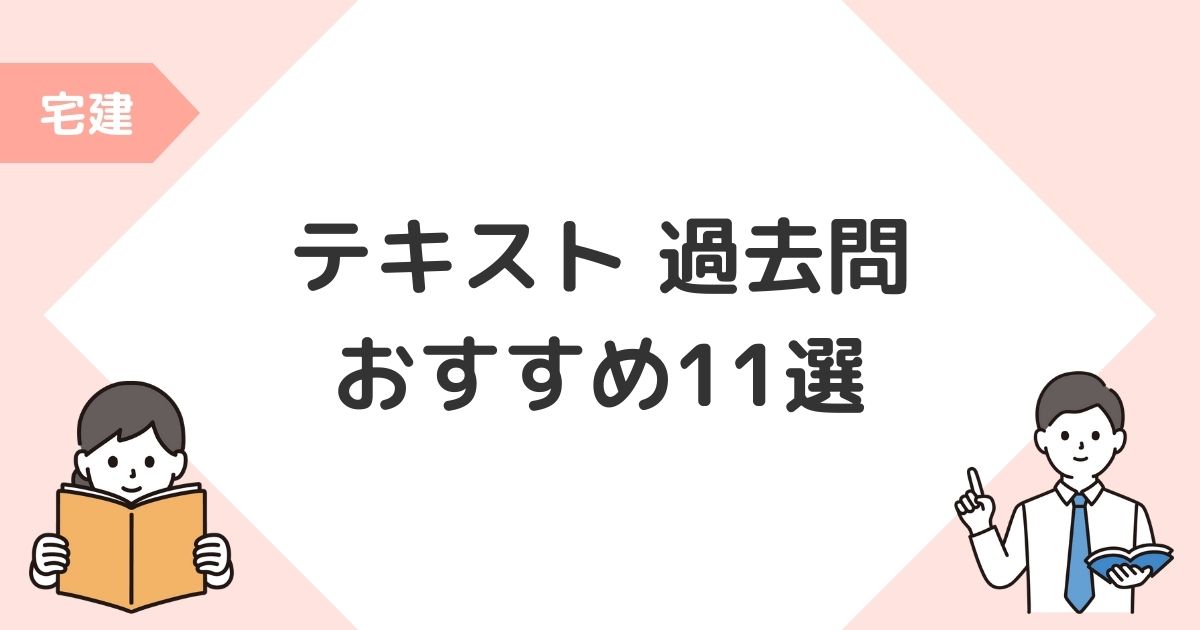
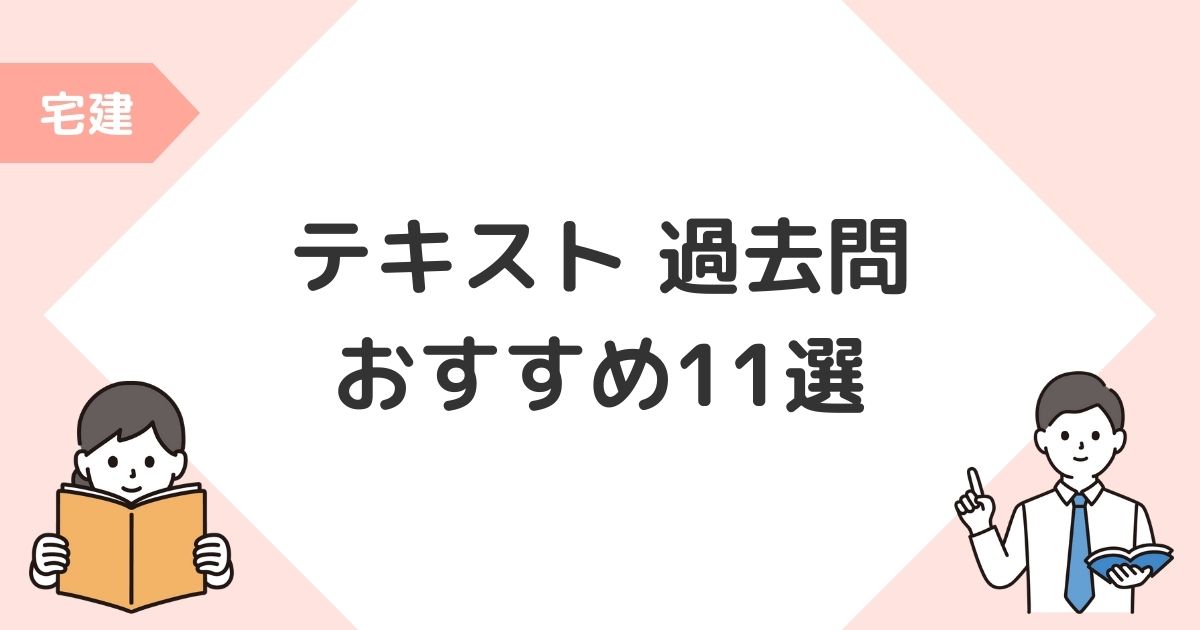
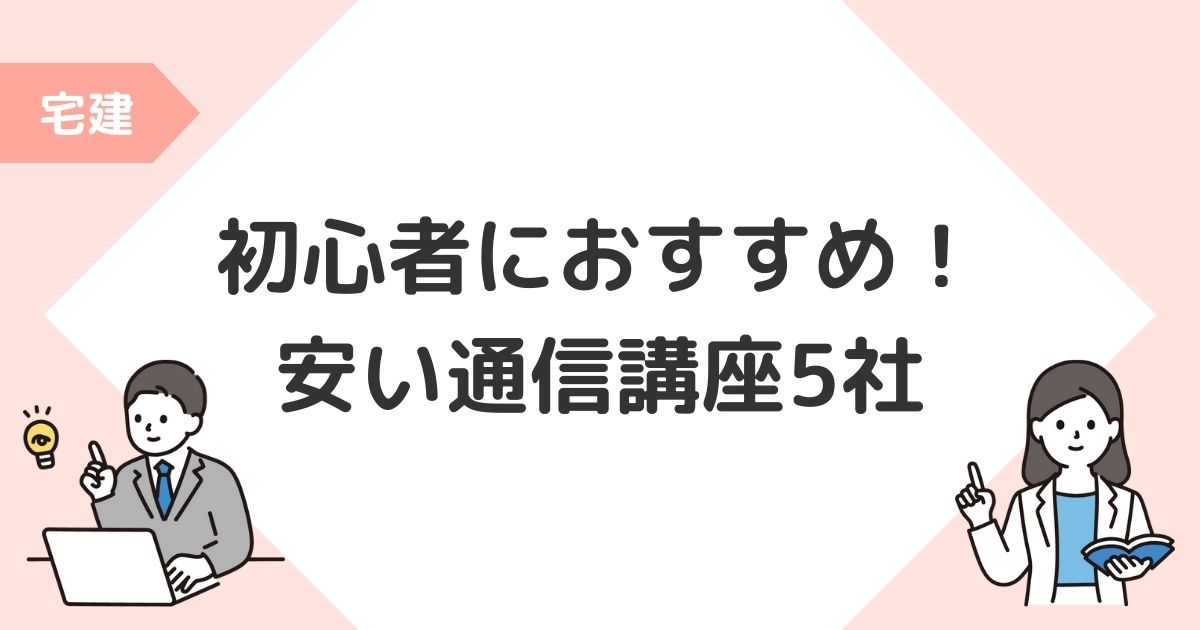
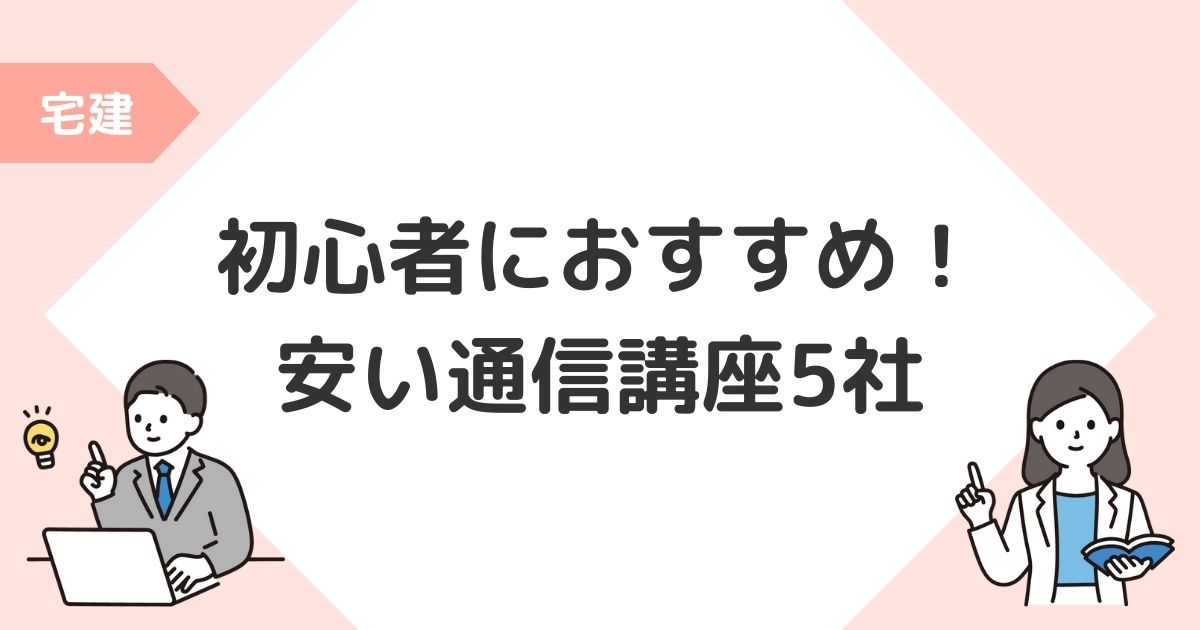
独学でおすすめのシリーズ
独学の場合、トリセツシリーズを買い揃えるのがおすすめです。
無料講義動画が充実しており、初学者の方も読みやすいのが特徴です。
おすすめの通信講座
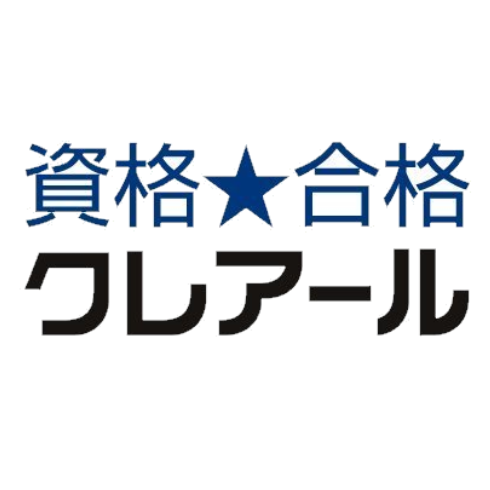
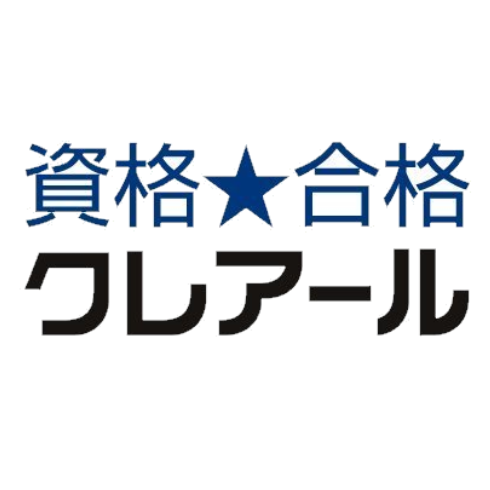
クレアールは、1998年に開講した長年のノウハウがある講座です。
セーフティコースを利用して今年の試験に合格すると、トータルで実質負担が33,434円に抑えられます。
本試験の受験料(8,200円)もクレアールが出してくれるので、お得に最短で合格を目指せます。



コースはいくつかあるので、まずは資料を取り寄せて内容を確認するのがおすすめです。
今ならクレアールの書籍「宅建士試験 非常識合格法」も無料でゲットでき、情報収集に役に立ちます。
\早い者勝ち!カンタン1分で入力完了/
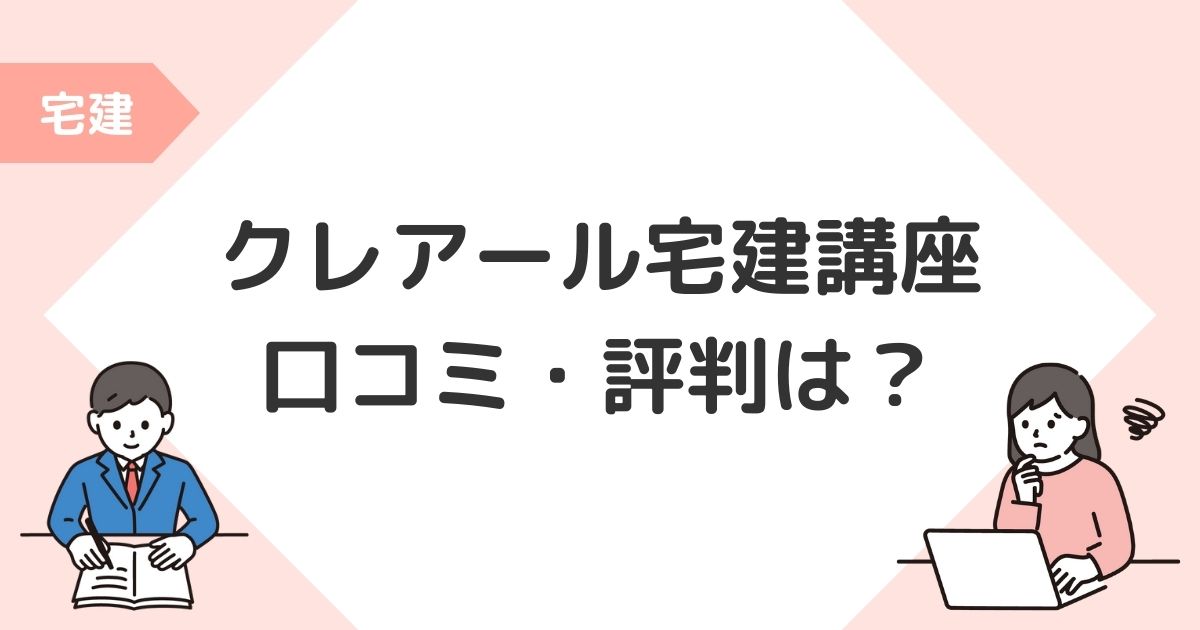
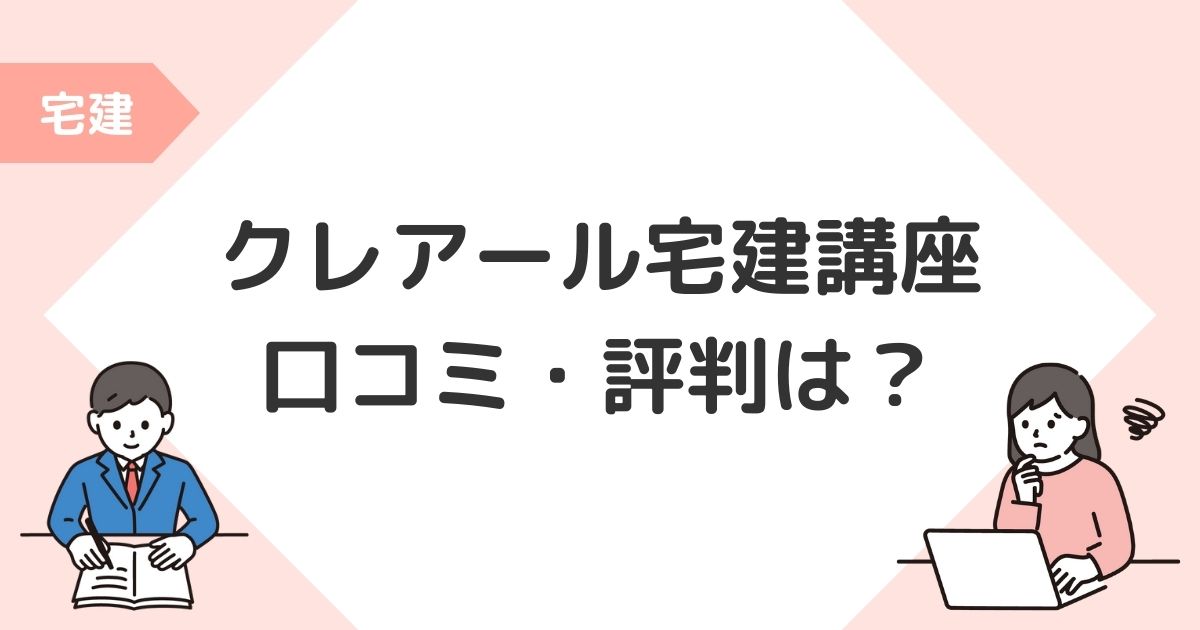
宅建は簡単すぎる・難しすぎるかは実際に勉強しないとわからない
宅建の難易度は人によって変わる以上、実際に勉強しないとわかりません。
一般的には普通〜やや難しいといわれていますが、個人差があります。
難易度について考えている時間があったら、先ほど紹介した勉強戦略に沿って下準備をし、勉強を始めてみることをおすすめします。